佐々木敦と南波一海によるインタビュー連載「聴くなら聞かねば!」には、前回に引き続き作詞家の児玉雨子が登場。今回は佐々木がアイドルソングの魅力に目覚めるきっかけの1つになったというアンジュルム「46億年LOVE」の詞作にまつわるエピソードを入り口に、コロナ禍以降に訪れたという作詞家としての心境の変化やクリエイションの源泉であるという自らのオタク気質について児玉が大いに語る。
構成 / 望月哲 撮影 / 臼杵成晃 イラスト / ナカG
グループのカラーを理解したうえで、あえて乗らないときもある
南波一海 そろそろ歌詞についての細かい話を聞いていきましょう。
佐々木敦 いよいよ(笑)。
児玉雨子 いいですね。歌詞の細かい話しましょう!
佐々木 まず、僕がアイドルに興味を持つきっかけになった曲の1つが、雨子さんが歌詞を手がけられたアンジュルムの「46億年LOVE」という大名曲だったんですよ。
児玉 いやいや、とんでもない(笑)。ありがとうございます。
佐々木 アンジュルムというグループのイメージって、なんとなくあるじゃないですか。それに対して雨子さんは、どんなふうに向き合って歌詞を書いてるんですか?
児玉 歌詞に関してはグループのカラーを理解したうえで、ガッツリ乗るときもあれば、あえて乗らないときもあります。イメージに合わせすぎると、いずれセルフパスティーシュというか、「こうすればいいんでしょ?」って、表現が内側にどんどんこもっていってしまうので。もちろん「今はこのイメージで固めたほうがいいんじゃないかな?」っていうときは乗りますけど。
佐々木 なるほど。
児玉 ちなみに「46億年LOVE」のときは、アンジュの「オラオラ!」って雰囲気にあまり乗らないようにして。職業音楽作家って、そういうイメージになんのてらいもなくドーンと乗れちゃう人の方が向いていると思います。私もそういうところがあるんですけど、それをやり続けるとファンもメンバー本人も飽きてしまうから、ブレーキをかけるようには気を付けています。ちょっと冷静になるというか、クールダウンしようと。全然できてないですけど(笑)。
佐々木 アイドルの楽曲って時系列順に並べてみると、一種の成長譚みたいにつながってることがあるじゃないですか。それも良し悪しだと思うんです。下手にうまくいっちゃうと次の展開が読めてしまったりとか。グループのカラーやストーリーに作家がどこまで乗ったらいいのかという問題はありますよね。
児玉 本当におっしゃる通りです。変な言い方すると、乗ることはいくらでもできるんですよ。でもそうすると結末がなんとなく見えてきちゃう。それに、作家が全力で乗っからないほうが見てる側からしたら楽しかったりするじゃないですか。予想を裏切るというか。裏切られる楽しさというのがあると思うので、それをどこまで意図しないで天然でやれるか、もしくは計算して天然っぽく見せられるか。私はプロデューサーではないし、楽曲の方向性を決める権限がないから、下手に口を出すことしかできないですけれど。
佐々木 でも口は出しますよっていう(笑)。
児玉 最近はけっこう迎合してます(笑)。長いものに巻かれてますよ!
佐々木・南波 あははは(笑)。
児玉 プロデューサーだったら、ある種の天然度合いがその人の才覚なのかなって思いますけど、職業作家となると、いかにグループを俯瞰して「今ズラしたほうがいいですよ」って言えるか、さじ加減ができるかどうかだと思います。
南波 メンバーも時とともに変化していくから、その時々で出てくるものが変わっていくこともありますよね。
児玉 変に物語を作っちゃって「あなた、この通りに動きなさいよ」って言わないほうが面白かったりするし。だから私はグループの物語を感じ取っても、あえて見て見ぬ振りをしているときもあります。ざっくり斜め読みするくらいで(笑)。
繊細な感情を歌詞にできるタイミングが来てる
佐々木 例えば「46億年LOVE」の中で描かれてる女の子が、何年後かに「ミラー・ミラー」の女の子になるとか、あるいは同じ人のある面とある面が別々の曲に分かれて出てるとか、歌詞の中に描かれた人物が雨子さんの中でつながっているようなところはあるんですか?
児玉 毎回新しくはしてるんですけど、たぶんグループの傾向があるので似たりよったりはすると思いますね。コロナ禍以降、ハロプロのリリースペースが落ちて、アニソンとか書いてると歌詞について考え直す機会が多くて。作風を激的に変えてもいいのかなとか思いました。最近自分の仕事についてちゃんと考えられるようになったから、いいクールダウンになっています。
佐々木 以前南波くんと対談したときも、コロナで我に返らざるを得ないから、今はみんながいろいろ考える時期なんじゃないかという話をしていて。この状況をなんとか反転させて未来につなげていかないと。
児玉 そうですね。コロナ禍以前と同じことをしてちゃいけない。今までは「ライブで歌って盛り上がる曲を」って発注がけっこうあったんですよ。でもそういう歌詞って、そんなに考えて書かなくていいんです。ライブでもお客さんが、すでに熱中して聴いてくださってるから。逆にあんまり複雑な感じで書くとワケわかんないじゃないですか。ダイレクトに「エモい!」だけのほうがいい。
佐々木 ブチ上がればいい。
児玉 そう、ブチ上がればいい。すばやく効くように。でも最近は、そもそもライブがあまりできないし、お客さんも集まれない。集まっても人は少ない。あと配信とか放送を通じて、みんな自分のテリトリーの中でライブに接してるから、気持ちは高ぶってるけど、すぐに現実に戻りやすいじゃないですか。ライブに行ってフワーッとした気持ちで帰る、あのクッションの時間がないんで。だから日常と地つなぎの言葉で書かなきゃとすごく感じていて。「アガる!」って感じの曲じゃなくて、もうちょっと繊細な感情を歌詞にできるタイミングが来てるんじゃないかと勝手に思ってるんです。
佐々木 確かにそうかもしれませんね。
児玉 「音楽を止めちゃいけない!」みたいな言葉をよく目にしますけど、別にみんな家の中とかでは音楽を聴いてるから、私はそんなに悲観してないんです。まあCD売り上げに関しては悲観してますけど(笑)。ただ状況に応じて、歌詞の書き方というか、トーンを変えたほうがいいなっていうのはすごく思います。今までは現場性というか、“エモ”や”熱”に頼りすぎてたと思うんで。
佐々木 ライブで一番効果を発揮するタイプの楽曲ということですよね。みんなでひとつになって盛り上がるような。俺が完全に無縁な世界(笑)。
児玉 あははは(笑)。私もそれが苦手だったんですよ。一生懸命こねくり回して考えたものが、ライブでは単に面倒くさいものになってしまうんだって一時期ショックを受けていたんですけど。
佐々木 むしろそこで勝負できる感じになってきた。
児玉 はい。みんな家の中で冷静に聴いてくれるから。それにプライベートな空間で音楽を聴くようになったから、恥ずかしげもなくみんな泣けるじゃないですか(笑)。ライブ会場より逆に感情を出しやすいんじゃないかなって。
佐々木 すごく思い当たることがありますね。僕は1人でYouTubeを観て号泣してるんで(笑)。
南波 加賀楓(モーニング娘。'20)さんの加入動画で。
佐々木 脊椎反射的に毎回同じところで泣ける。泣くために観てるんじゃないかっていう(笑)。
児玉 あははは(笑)。そういう、今までできなかったことができるようになっているので、だったら自分も歌詞の書き方を変えなきゃだし。今までは「ちょっと伝わりづらいかな」って自分でフィルターをかけてたところがあったんですよ。ただ、アニソンではフィルターをかけていなかったんです。なぜかと言うと、アニソンのオタクって解釈大好きなんで。考察ブログをずっと書き続けるみたいな人が多いんです。
佐々木 なるほど!
児玉 「このキャラの思想だから、物語の本編ではこういうことがあって」みたいなことをすごく熱心に書いている方が多いんですよ。だからあんまりこういうのは書いちゃダメだよねっていうのはナシで書いてたんです。スタッフさんにも「歌詞にこういう一節があったから、ゲームのシナリオにセリフを加えました」みたいなことを言われたり。アイドルソングは言葉がライブの熱気に負けてたんですよ。
南波 ライブで盛り上がるためのツールとしての意味合いが強くなりすぎて。
児玉 はい。それがなくなったから、今後アイドルソングの仕事は減るかもしれないですけれど、曲単体、作詞だけで捉えたら、「けっこう私、これからのほうが楽しく書けるんじゃない?」って思ってて(笑)。
南波 いやー、素晴らしいですね!
恋人たちはいつだって会いたくても会えない
佐々木 例えば今、映像の世界だと「登場人物はマスクをしてなければいけないのか?」っていう問題があると思うんです。今後、ワクチンが開発されたりしてコロナが収束したとき、映画史やドラマ史の中で一時期だけ登場人物がみんなマスクをしてる時代があるということになってしまう。それをコロナ禍のリアリティだと考えるかどうかで、映像関係の人はけっこう悩んでると思うんです。それってポピュラーミュージックの歌詞にも関係してくる問題じゃないですか?
児玉 あります、あります。特にアイドルの歌詞は。逆にアニソンはフィクションの世界なので、あまり関係ないんですよ。
佐々木 ああ、そうですよね。
児玉 コロナ禍の影響で当然、恋愛も変わるだろうし、そこはやっぱり意識します。作詞・作曲家の仲間内でこれからのラブソングの歌詞の話をしてるときに、「マスク越しのキスはファーストキスに入るの?(笑)」とか言って大笑いしてたんですけど(笑)。
佐々木・南波 あははは(笑)。
児玉 でも、あまりにも“今”すぎるキーワードは考えてしまいますね。ちょっと前だったら歌詞に「スマホ」って入れるのは恥ずかしいとか。
佐々木 その前は「携帯」とか「ピッチ」とかあったわけだけど全部死語になってしまった。
児玉 なので意識しすぎてはいないけど、こういう時代に生きているということは受け入れて書くようにしています。「マスクを付けて」みたいな描写はいちいち書かないけれど、「会いたいね」という言葉はやっぱり使いますし。そもそもコロナウイルスがなくても、恋人たちはいつだって会いたくても会えないことが多いから(笑)。
南波 歌詞の中では。
児玉 はい(笑)。なので、あんまり変えなくてもいいかなとは思って。あとは「テレビ電話する」っていうのが恥ずかしいくらいで(笑)。でも確かに映像の方々は戸惑うだろうなって思います。
南波 ヒップホップとかは早いですけどね、そういうのは。
佐々木 ラップは即時反応の言語芸術だからね。状況にすぐさま対応できる。
児玉 確かに。ヒップホップとかに対して、J-POPやアイドルの歌詞はある種セルアウト的というか、「ダセー!」って言われるくらいまっすぐ行かなきゃいけないところがありますよね。現実見ろよ、と揶揄されながらも、私は横目で現実を見てるような状態で歌詞を書いています。
南波 視界には入ってるけれどっていう。
児玉 そう、視界には入ってるけれど(笑)。そこを崩したら誰も王道を歩かなくなるから、なんと言われようと、まっすぐ明るい未来だけ見て歩いていこう、とは思ってます(笑)。現実からも未来からも逃げない。
オタクであることが自分の作風に影響を及ぼしてる
佐々木 これはポピュラーミュージック全般に言えることだと思うんですけど、テレビやラジオで放送されるときって楽曲がフルコーラス流れることってほぼないじゃないですか。だから歌い出しとサビに強いメロディや言葉を持ってくるのが従来のやり方だったと思うんです。でも雨子さんの歌詞って、全部が全部そうではないと思うんだけど、フルコーラスで聴かれることを想定して物語や世界観が作られてる気がするんですよね。一番わかりやすい例は、つばきファクトリーの「抱きしめられてみたい」。僕、あの曲がすごく好きなんですよ。
児玉 ありがとうございます!
佐々木 あの曲って、最後の最後で逆転するっていう感じの歌詞じゃないですか。ミステリ小説に「最後の一撃(フィニッシング・ストローク)」って用語があるんですけど、あれはまさにそれだと思う。ああいうタイプの歌詞って、あんまりないと思うんです。最近のヒット曲って、だいたい序盤でブチ上がって、そこからなんかいい感じで進んでいくか、サビの高揚感をひたすら反復するかのどちらかが多い。でも雨子さんの歌詞には、最後まで聴かないとわかんないみたいなところがあって、すごく独特だなと思うんです。
児玉 それってたまに言われるので、以前、自己解釈してみたことがあったんですけど、たぶん私がニコニコ動画世代であることが関係してるのかなと思ったんです。
南波 へえ。
児玉 ニコニコ動画と、あとはボカロですね。ボカロ曲って楽曲と映像で1つの物語を作るという感じがあって。私は米津玄師さんが“ハチ”と名乗っていた頃にボカロ曲をよく聴いていたんですけど、みんな当たり前にフルコーラスで曲を聴くんですよね。しかも延々繰り返して。
佐々木 そうですよね。テレビと違って繰り返して観ることができるし。
児玉 私は音楽番組よりもニコ動やYouTubeを観て育ってるから、当たり前にみんなフルコーラスを聴くもんだと思っていたんです。だから、このお仕事をするようになってディレクターさんから「Aメロとサビで……」って言われたとき、自分がネット入り浸り人間だと改めて思い知らされました。そこに世代の差を感じることがあります(笑)。で、それは同世代でも、オタクか非オタクかでかなり違っていて。オタクはちゃんと曲を全部聴くんで(笑)。アニソンオタクもそうだし。私はオタクだからフルコーラス聴かれること前提で歌詞を書いてるんだと思います。
佐々木 僕もそうですけど、オタクは最後にドンデン返しが来るのが好きですからね(笑)。
児玉 もう、パチパチ(拍手)って感じじゃないですか(笑)。
佐々木 「お見事!」っていう(笑)。
児玉 「よし! 解釈ブログ書こう!」みたいな(笑)。
佐々木・南波 あははは!(笑)
児玉 だから解釈ブログを書く人の気持ちもすごくわかるし。私も「うわー! それすごいねー!」って思ってたから。オタクであることが自分の作風に影響を及ぼしてると思います。若者ぶるわけじゃないんですけど、たぶんそうなんだろうなと。でも、こういうことができるようになったのって、米津玄師さんとかが出てきたことが大きいです。今まで日陰者だったオタクが、J-POPシーンにいてもよくなった。しかも私たちよりも10コくらい下の若い人たちは、それが当たり前になってる。
佐々木 物心ついたら、すでにネットがあった世代。
児玉 もう、私も彼ら彼女らからすれば、ひと昔前の感覚かもしれません。きっと繰り返しだと思うんですよ。瑛人さんみたいにシンプルなわかりやすいものが意外と流行ったりするときもあれば、それに飽きたらやっぱり解釈が必要なものが流行ったり。私はネットが普及したおかげで選択肢が増えたと思っています。それまでは1つの流行がテレビやラジオだけで回っていたけど、ネットの普及以降いろんな場所で流行が回り始めるようになったんじゃないかな。
ハロプロのディレクターさんが、だんだんオタクサイドに(笑)
南波 ちなみに自分が歌詞を書いた曲が、ライブで1ハーフとかで歌われると「うーむ……」って思ったりするんですか?
児玉 「あっ、なるほどね」っていう感じです(笑)。でも対策がちゃんとあって。テレビの音楽番組用に歌詞を書いてた人たちって、最後のサビで1番のサビを繰り返すんですよ。でも私は2番のサビを繰り返しにしたり、落ちサビだけ変えちゃったり、あとはラストサビ2行だけ変えるとか無駄な抗いをしていて。2番サビを繰り返してくれって言ってるのにしてなかったら「なんで?」ってずっと言ってますね(笑)。
南波 それは面白い。
児玉 だっておんなじこと何回も聴かされてつまんないじゃん、っていうのがオタクサイドの言い分なんですよ。でも、もっとライトな層には「ゴチャゴチャ言ってると覚えられない」って言われちゃうんですよ。この分断!(笑)
南波 あははは。分断(笑)。
児玉 自分はオタクサイドだから、ちょっとだけ変えるとか、そういうことをするのかなと思いますね。
佐々木 通常、ヒット曲の掟はリフレインが勝負だけど、それに対してなんとかして反抗したいんですね(笑)。
児玉 そうなんですよ。声優さんもオタク上がりが多いんで、「最後変えてください」ってよく言われます。「最後の2行だけ変えてください」と言われ、「だよね!?」みたいな(笑)。やっぱりオタクはそうなんですよね。基本、「もっとくれ、もっとくれ」ってなっちゃうんで(笑)。
佐々木 いやー、でも「抱きしめられてみたい」の最後2行の衝撃たるや、すごかったですよ。
児玉 あれは、ディレクターさんが「変えたいんだけど」って言ってくれて、「いいんですか!?」みたいな。
佐々木 「オチを付けていいんですか?」って。
児玉 そう、「本当にいいんですか!? やっちゃいますけど!?」みたいな感じだったので(笑)。ハロプロのディレクターさんたちは、もともとテレビ寄りの方々だったんですけど、だんだんオタクサイドに落ちてきましたね(笑)。感覚がどんどんオタクっぽくなってきた。「やっぱ最後が違うといいよね!」とか言い始めたんで、どんどんこっちに染まってきてる感じです(笑)。
<次回に続く / 前回はこちら>
児玉雨子
1993年12月21生まれの作家、作詞家。モーニング娘。'20、℃-ute、アンジュルム、Juice=Juice、近田春夫、フィロソフィーのダンス、CUBERS、私立恵比寿中学、中島愛といった数多くのアーティストに歌詞を提供する。アニメソングの作詞も多数行っている。「月刊Newtype」で小説「模像系彼女しーちゃんとX人の彼」を連載中。
佐々木敦
1964年生まれの作家 / 音楽レーベルHEADZ主宰。文学、音楽、演劇、映画ほか、さまざまなジャンルについて批評活動を行う。「ニッポンの音楽」「未知との遭遇」「アートートロジー」「私は小説である」「この映画を視ているのは誰か?」など著書多数。2020年4月に創刊された文学ムック「ことばと」編集長。2020年3月に「新潮 2020年4月号」にて初の小説「半睡」を発表。8月には78編の批評文を収録した「批評王 終わりなき思考のレッスン」(工作舎)が刊行された。
南波一海
1978年生まれの音楽ライター。アイドル専門音楽レーベル「PENGUIN DISC」主宰。近年はアイドルをはじめとするアーティストへのインタビューを多く行ない、その数は年間100本を越える。タワーレコードのストリーミングメディア「タワレコTV」のアイドル紹介番組「南波一海のアイドル三十六房」でナビゲーターを務めるほか、さまざまなメディアで活躍している。「ハロー!プロジェクトの全曲から集めちゃいました! Vol.1 アイドル三十六房編」や「JAPAN IDOL FILE」シリーズなど、コンピレーションCDも監修。

関連記事

再び動き出したEXOとBTS|2026年1月のK-POP

ハロプロの5人がインフルエンザB型に感染、今週土日のコンサートは欠席
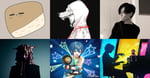
【マイベストトラック2025】ネットクリエイター編:厚揚げろが。、雨良、岩見陸、きくお、ちぐさくん、まらしぃが選ぶ3曲

「EIGHT-JAM」いしわたり淳治、蔦谷好位置、川谷絵音が選んだ2025年ベスト10曲発表

櫻坂46山﨑天が「ザ・グレイテスト・ヒッツ」今夜出演、ニューヨーク世代のヒット曲に驚き

米津玄師、紅白歌合戦の「IRIS OUT」と「さよーならまたいつか!」映像YouTubeで公開

ハロプロ所属アーティストが渾身のソロパフォーマンスで真剣勝負!「ソロフェス」5年ぶり復活

あなたが決める!2025年の音楽トップニュース

「紅白歌合戦2025」タイムテーブル発表!全出演者の登場時間帯・歌唱曲一覧が明らかに



