2010年代のアイドルシーンを複数の記事で多角的に掘り下げていく本連載。ひさびさの更新となった今回はアイドルシーンにおける“ダンス”に着眼し、前編、中編、後編の3本立てで記事を展開する。グループとしてもメンバー個人としても、歌唱力と同様にダンススキルの高さは大きな武器となり、ほかのアイドルとの違いを生み出す個性につながるが、アイドルが踊る“ダンス”にさまざまなスタイルが生まれたのも、ファンがその文化を楽しむようになったのも実は2010年代に入ってから。どのような背景があって、アイドルのダンスは進化していったのだろうか。
記事の前編となる本稿では、アイドルカルチャーに革新をもたらしたモーニング娘。の“フォーメーションダンス”にフォーカスし、このダンスの生みの親と言われている振付師・YOSHIKO氏にインタビュー。フォーメーションダンス誕生の裏側を振り返ってもらった。
取材・文 / 小野田衛
アイドルのダンス史におけるターニングポイント
これまで当連載では2010年代のアイドルシーンをさまざまな角度から分析してきた。いわゆる“アイドル戦国時代”の到来によって、何がどのように変わったのか? 最も大きな要素の1つとして、ダンスが注目されるようになった点が挙げられる。
もちろん1970年代に日本で女性アイドルというジャンルが確立して以降、ダンスは常にパフォーマンスの一部として存在していた。たとえそれが軽いサイドステップ程度のものであったとしてもだ。しかし、考えてみてほしい。森昌子、桜田淳子、山口百恵の“花の中3トリオ”、、松田聖子や中森明菜ら代表される80年代初頭のアイドル……どの時代でも「歌がうまい」と称賛されるアイドルはいたが、「ダンスがすごい」「動きがそろっている」といった評価軸で語られることはほとんどなかったのではないか。
日本中の子供たちがこぞって振付を覚えて真似したピンク・レディー、「LOVEマシーン」などメガヒットを連発していたときのモーニング娘。ですら、コミカルな振付が話題になることこそあれ、メンバーのダンススキルに言及する声は極めて限定的だった。現在の目で見ると後藤真希の動きなどは当時からキレキレだったが、観る側のリテラシーが追い付いていなかったのだろう。楽曲、歌唱力、ビジュアルなどに比べて、アイドル文化の中でダンスが軽視されてきたことは間違いない。
ももいろクローバーZのえびぞりジャンプに代表されるアクロバティックなステージング。AKB48に対するカウンターとして機能したSKE48の汗が飛び散る妥協なきパフォーマンス。でんぱ組.incの人工的な高速ビートに呼応するような演劇的振付。2010年前後から各グループがダンス面で自己主張をぶつけるようなり、ファンも振付に対する関心を高めていった。そんな中で大きなターニングポイントとなったのが、モーニング娘。の提示した“フォーメーションダンス”である。
フォーメーションダンスとは、メンバーが激しく場位置を移動しながら集団としてのダンスで魅せる集団行動のようなアプローチを指す。後世に与えた影響は絶大で、現在においては大所帯グループの必須科目とも言えるほど。そしてこれを生み出したのが、長年にわたりハロー!プロジェクトに携わっている振付師のYOSHIKO氏とされているのだ。
「つんく♂さんは本当に全部をプロデュースしていた」
文字通り、アイドルカルチャーの文脈を一変させたフォーメーションダンス。その誕生の裏側には何があったのか? 最重要キーパーソンのYOSHIKO氏は「私は2000年の『黄色いお空でBOOM BOOM BOOM』(黄色5)からハロプロに関わっているんですけど……」とプロデューサーのつんく♂との関係から説明し始めた。
「つんく♂さんは本当に全部をプロデュースしていたんです。楽曲はもちろんだけど、歌い方から、衣装から、髪型から、セットリストから、ステージ監督まですべてを。ですから振付に対しても、毎回ものすごく細かい指示を出されていました。『今回はこういうテーマ。◯◯っぽく全員で踊る感じにしてくれ』というように指示はいつも具体的でしたね。それをモーニング娘。だけじゃなくて、Berryz工房や℃-uteやスマイレージにも同じように全部やっていました」
「メンバーは直接つんく♂さんと会う機会がなかなかない。なので代わりに私たちが踊り方や歌い方のポイントをつんく♂さんから伝えられるんです。そして、それを私たちがメンバーに伝言していく。『もっとリズムを気にしてって言われていたよ』というふうに。なおかつリハーサルのV(映像)は必ず一緒にチェックしていました。そこでつんく♂さんからダメ出ししてもらって、『うん、だいぶよくなったね』とOKをもらう。『○○には、もっとしっかり歌わせておいて』と気になったメンバーを名指しすることも多かったです」
つんく♂のディレクションに関するYOSHIKO氏の説明は続く。
「振付の打ち合わせが始まったら、まずいきなり自分で踊って伝えてくれました。『こういう感じで』と実際に身振り手振りで体を使って表現してくれるから、ニュアンスは汲み取れるわけですよ。『こういうことをやりたいのかな』って。それで実際に自分たちが振付を考えて、『こんな感じで作ってみましたけど』って見せる。そこで『そうそう!』と言われることもあれば、『いや、全然違うな』って言われることもありましたね。指示が変わることもありました。『閃めいちゃったけど、ごめん、やっぱり違ったわ』という感じで」
2012年の「ワクテカ」で個人より団体として見せる方針へ
つんく♂が単にサウンド面だけを管轄する音楽プロデューサーでないのは明確だ。グループや楽曲についてのビジョンが、細部に至るまで頭の中でイメージできていたのだろう。そんな中で、つんく♂からYOSHIKO氏に「ダンスを団体で見せる感じで作ってほしい」「歌割とか気にしなくていいから、大人数で移動するイメージで」というオーダーが届いた。その楽曲が、2012年にリリースされた51枚目のシングル「ワクテカ Take a chance」だったという。
なお、フォーメーションダンスは当時モーニング娘。が推し進めていたEDM路線のサウンドとセットで語られることが多いが、EDMに主舵を切った49thシングル「恋愛ハンター」の時点ではまだフォーメーションダンスは導入されていなかった。このことは譜久村聖も同様の証言をしているが、YOSHIKO氏は以下のように語ってくれた。
「結局、その前の時代というのは、メインで歌うメンバーを目立たせていたんですよ。『この曲は高橋(愛)を目立たせたい』『今回は田中(れいな)で』みたいな指定がありましたし。だから振付師としても、自然とその子をセンターに置くようになるわけですね。仮に場位置がズレたとしても、すぐ戻れるようにしていました。あとは、それ以外のところで歌割に合わせて目立たせるメンバーに変化をつける、といった発想でしか基本は作っていなくて。道重(さゆみ)がよく『歌割が“あ”しかなかった』とか自虐気味に語っていたじゃないですか。でも、あれは本当にその通りなんですよ。高橋がリーダーだった頃は私も“歌割が少ない=目立たない”というのが当たり前だと思っていましたしね。それが急に2012年の『ワクテカ』で個人より団体として見せるに方針転換したんです」
ここまで話を聞いて、1つの疑念が浮かんできた。もしかしてフォーメーションダンスを“発明”したのは振付師・YOSHIKO氏ではなくて、プロデューサー・つんく♂だったのではないか? そのことを恐る恐る口にした瞬間、YOSHIKO氏は若干食い気味に答えてくれた。
「まさにその通りですよ! 少なくとも言い出しっぺは確実につんく♂さん! 『もっと全体を見せたいんや』って話を切り出してきたわけですから。あくまでも私はそれを形にする手伝いをしただけなんです。じゃあ具体的にはどうやって団体で見せるか? そこで私が参考にしたのは、日体大とかでやっている“集団行動”。ちょうどあれがテレビのニュースとかで取り上げられ始めた時期だったんですよね。練習風景とか、先生の指導方法が紹介されていて。それを見てすごいなと思ったし、興味を持っていたんです」
グループアイドルのジレンマに対する1つの解決策
大変なのは、ここからだ。何しろ前例のないことをやるため、すべてが手探り。メンバーの戸惑いも大きかった。場位置1つとっても、それまでは「最初は1番! その次は2番に移動!」などと言っていたのが、「1.25」や「0.75」などの細かい数字が飛び交うようになる。加えてリハーサルしていたスタジオではスペースの関係で、踊るときの場位置の番号が限られていたので、メンバーの人数が増えても必ずその中で収めなくてはいけないという制約があった。
「具体的に言うとセンターが0番で、左右の端っこが3.5。そこに全メンバーを収めなくちゃいけなかったんですね。じゃないと、映像に収められないという問題も当時はありましたし。それに加えてフォーメーションダンスの場合は左右だけなくて、前後もそろえなくちゃいけないわけで」
さらに実際のコンサート会場となると、そのほかの問題も出てくる。ステージ上にセットが組まれるため、踊るスペースが狭くなるのだ。
「結局、フォーメーションダンスのためにセットの作り方もイチから変えることになりました。スタッフさんが1階のフロア部分をすごく広く作ってくださいましてね。けっこう大掛かりな話になっちゃったけど、そうしないとフォーメーションダンスは成立させられなかったんです」
曲間の移動距離が長くなると、メンバーは「なんとか間に合わせたい」という気持ちが先走るようになる。すると、全体としてフォーメーションがそろわなくなる。ここで大事なのは「みんなでそろえよう」という共通認識なのだという。この「周りに合わせてラインをきれいにする」という意識を徹底させるのに時間がかかったとYOSHIKO氏は振り返る。
「あと、現実的な話としてあったのがメンバー間の実力差。あの時期は9期、10期の若い子たちが一気に入ってきて、ダンス未経験者も多かった。普通、そういう場合は踊れる子を前に持ってきて目立たせるものなんです。うまい子がセンターで踊っていると、全体としてもダンスが上手なグループという印象になりますから。つんく♂さんも最初は『上手なメンバーにやらせればいいよ』という考え方だったんです。当時で言うと、鞘師(里保)、石田(亜佑美)、譜久村、小田(さくら)……いわゆる経験者組ですよね」
10期メンバーの加入直後、筆者も4人がダンスレッスンする様子を取材させてもらったことがある。素人目に見ても、大きな差があることに驚いた。具体的には難なく振り入れをこなす石田と工藤遥の経験者組と、先生に怒られながら涙する未経験組の飯窪春菜と佐藤優樹。だが、これは当然なのかもしれない。スポーツや楽器演奏でもそうだが、いきなり未経験者が経験者と同じレベルでやるというのは土台無理な話だ。
「結局そこなんですよね。その問題はグループアイドルに常につきまとってくるんです。踊れない子は、どうしたって後ろとか端っこのポジションになってしまう。道重もそうだけど、飯窪なんかも何もできない状態で入って、ものすごく苦戦していた。それでもやっぱり見せ場は作ってあげたいじゃないですか。たとえ少しだけであったとしても。そのジレンマに対して、フォーメーションダンスは1つの解決策を示したとは思っているんですよ。というのも、つんく♂さんの歌割というのはものすごく細かい。歌割が少ない子はテレビで一瞬しか映らないし、コンサートだったらモニタに抜かれづらい。その一瞬で見せ場を作るため、フォーメーションを動かすという面もあるんです。要は目立たせる人をどんどん変えていきたかったんですよ。それで『じゃあ、もうここは回転しちゃえ』みたいなことになっていった」
当時、グループ内でダンス面を牽引していたのは鞘師と石田だった。この2人は幼少期からのダンス経験者であるものの、ハロプロ以外の外部組織で学んでいるのが特徴。それに対して、譜久村や工藤はハロプロエッグ(現・ハロプロ研修生)で研鑽を積んできたという経緯がある。結果的には“外の血”が入ることがプラスに作用したとYOSHIKO氏は見ている。
「田中が卒業(2013年5月)してからは、道重が1人だけ年齢の離れた状態でリーダーをやっていましたよね。それも全体の“まとまり”につながったんです。年下のメンバーたちは道重のことを本当に心の底から尊敬していて、『道重さん、教えてください!』というモードでチームとしての一体感があった。『道重さんに恥をかかせるわけにはいかない』という気持ちと『早く道重さんに追いつきたい』という気持ちの両方を持っていてね。みんなが『道重さんのために!』という旗印のもとに突き進んでいたんです」
道重の卒業後、グループ内の雰囲気が一気に変わったことにYOSHIKO氏は驚いたという。それまでカリスマ性のある道重に対して横一列で忠誠を誓っていたメンバーたちが、個々の野心をメラメラと見せるようになったのだ。そこで逆説的に「そうか。今までは道重の下でまとまっていたチームだったんだな」と気付くことになる。その角度で考えると、フォーメーションダンスの誕生には、道重がリーダーだったことも大きな要素としてあったかもしれない。話の時系列をフォーメーションダンスが登場した2012年に戻そう。
「『ワクテカ』以降、『前回の延長で』ということがしばらく続いたんですね。もちろんまったく同じことをするわけではなく、その都度『次は何をやろう?』と頭を悩ませてはいましたが。特に印象に残っているのは『愛の軍団』かな。あの振りは軍隊をイメージしているんです。兵隊さんが少し無機質な感じでザクザク行進しているような動き。それも直接つんく♂さんから言われましたね。本人が実際に身動きを交えながら、『行進がいいかな』って」
「自分の考えた振りを真似してくれる」ことが最大の喜び
フォーメーションダンスが大きく注目されたことで、モーニング娘。はセールス的にも快進撃を続けた。世間からも「完全V字回復」「第2次黄金時代の到来」などと評価されるようになったが、当のYOSHIKO氏は振付が騒がれていることをまったく把握していなかった。周囲から「話題になっているらしいじゃん」などと言われても、「えっ、そうなんですか? どこで言われているんですか?」とキョトンとする有様だったという。
「やっている立場からすると、一番大変なのはリハーサル期間なんですよ。作品が世に出る頃にはもう次の曲に取りかかっているから、感覚的にタイムラグがある。つんく♂さんもフォーメーションダンスが話題になっていることを知らなかったくらいですから。それで『だったら、これに名前を付けようか。何がいいかな?』『うーん、集団行動ってそのまま使うわけにもいかないと思うので、強いて言えばフォーメーションですかね』『だったら“フォーメーションダンス”でいいか』みたいな感じ。けっこうぼんやりした会話でしたよ。少なくとも『これを流行らせる!』とか、そんな発想は一切なかったです」
現在、YOSHIKO氏はハロプロ以外の現役アイドルから「モーニング娘。さんがフォーメーションダンスをやっている姿を見て、私もアイドルを目指すようになりました」などと声をかけられる立場になった。うれしいと同時に驚きと戸惑いも感じるそうだ。「純然たるダンスのレベルだけをとったら、ハロプロより高度なことをやっているところはいっぱいある」というのがYOSHIKO氏の見立て。むしろ「ダンスがうまい子もいれば下手な子もいるのがハロプロの特徴」と捉えている。しかし「難しいことをやっているから偉い」という単純な話で収まらないのは、あらゆる芸事に共通して言えることだ。
「面白いなと思うのは、例えばフォーメーションダンスをやっていなかった頃に卒業したメンバーたちがフォーメーションダンスを見ながら『もう私にはあんなことできない……』なんて言ったりするんですよ。私なんかは『全然へっちゃらだよ』って思うんだけど、そこは頑なに『いやいや、絶対に無理です』と言ってきますから。だから結局、アイドルのダンスが時代とともに少しずつ進化しているのは確かなんでしょうね」
アイドルのダンスに一石を投じた「ワクテカ Take a chance」発表から約13年が経過した。その間、多くのグループが生まれては消え、さまざまなトレンドも誕生した。欅坂46やラストアイドルが“集団行動”的なアプローチを踏襲したこともあり、いまやフォーメーションダンスは決して珍しいものではなくなった。そんな現在のシーンをYOSHIKO氏はどう見ているのか?
「総じて言えることは、歌よりもファッションやダンス……要するに見た目が重視されるようになっていますよね。これは明らかにYouTubeの影響。ダンスの映像を気軽に観られるようになったのはすごく大きな変化だったと思う。だから単純に今の若い子はダンスを踊れる割合が増えているじゃないですか。すぐ手軽にダンスを始められる環境が整っているので。ハロプロでも最近は“まったく踊れません”みたいな子は少数派になっています。街のキッズクラス自体も増えているし、ダンスの先生につかなくてもYouTubeさえあれば見よう見真似で子供たちがダンスを始められる。そういう時代に日本もなったんです。そもそも昔は振付のことが話題になることもなかったですしね。これは興味の対象がダンスに向かっていなかったということで、そこは大きな時代の変化を感じます。YouTubeとかで真似して踊って、それをすぐさま自分のSNSに上げる時代に入っているんですから。そういう意味じゃ、今の若い子たちは本当にすごいですよ」
YOSHIKO氏には振付師として肝に銘じていることがある。振りを作る際は“会場で真似される様子”を必ず意識するのである。
「ハロプロのコンサートって、お客さんがすぐ振付を真似してくれるんです。新曲を初披露しても、歌が2番に入るとすでに振りコピできていたりする。私、最初にその光景を見たとき、めちゃくちゃ感動したんですよね。『すごい……。こんな真似してくれるんだ!』って驚いちゃって。忘れもしない、松浦(亜弥)の『LOVE涙色』のときでした。そこからはずっと考えていることは同じ。この仕事をやるうえで、『自分の考えた振りを真似してくれる』ということに最大の喜びを見出しています。ただ、そうは言ってもフォーメーションダンスは真似できないだろうと思っていたんです。なぜなら、あれは一種の集団芸ですから。でも、一瞬で真似された(笑)。ホントみんなすごいなって感動しますよ。やっぱり一番大事なのはコンサートで盛り上がることですからね」
奇しくもこの「真似したい」というマインドは、フォーメーションダンスが時代を突破した大きな要因となる。“踊ってみた動画”カルチャーの隆盛という背景もあり、「自分たちもやってみたい」と若者たちがモーニング娘。の動きを研究するようになったのだ。プロデューサーや振付師の思惑すらも飛び越え、「個人より全体を見せる」ダンスが急速にポピュラリティを獲得していく。
一方、グループ内部に目を移すと、メンバーは別のことも感じていた。中編となる次回は、当時のモーニング娘。のエース・鞘師里保が「至近距離から目撃したフォーメーションダンスの真実」を語り、卒業後も八面六臂の活躍を続ける立場から「2010年代のアイドルダンス」を再定義する。

関連記事

「CDTV ライブ!ライブ!」年越しスペシャルのタイムテーブル公開、ミセス、HANA、超特急、BE:FIRST、M!LKら76組の歌唱曲と出演時間は

新体制アップアップガールズ(2)大勝負のZepp DCワンマン成功「一緒に同じストーリーを作っていきたい」

ハロプロ30周年企画始動、来年サブスク解禁&「ハロ!コン 2026」を開催

都市型フェス「CENTRAL」来年も横浜で 出演者にYOASOBI、HANA、結束バンド、乃木坂46ら

年越し「CDTV」にミセス、HANA、超特急、M!LK、LiSA、モー娘。'26、&TEAM、キスマイら76組

モーニング娘。牧野真莉愛、25歳の誕生日に写真集発売
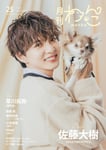
佐藤大樹とチワワが瞳輝かせる「月刊わんこ」特別版表紙、裏表紙には草川拓弥

超特急・草川拓弥の優しさにトイプードルも大満足「月刊わんこ」初表紙

モーニング娘。'25羽賀朱音&横山玲奈が晴れやかに卒業、リーダー野中美希はグループの進化を約束



