日本のアンダーグラウンドな音楽やアートを世界に紹介するという趣旨のショーケース的イベント「MAZEUM」(メイジアム)が、11月30日、12月1日の2日間にわたって京都の寺院やクラブなど6会場で開催された。出演アーティストは一般的なサーキットイベントからイメージされるラインナップとは一線を画したカテゴライズ不能な顔ぶれだったが、その特殊な内容にも関わらず結果としてイベントは大盛況となった。
本稿では京都在住の音楽評論家・岡村詩野が、このイベントの舞台となった京都という街の文化的な特異性について詳説しつつ、この2日間に何が起こったのかをレポートする。
特有の音楽文化をサポートしてきた、住民たちの目線
会場から会場へと移動するときの光景がまず痛快だった。にぎやかにショッピングをする10代の若者たち、スーパーのレジ袋を下げたおばあちゃんやおじいちゃん、ベビーカーを押す家族連れ、着慣れなさそうな和装の観光客、Tシャツにリュックの外国人……世代も国籍も超えたさまざまな人々が大勢入り乱れる週末の京都。その中で、パンフレットを開きながらキョロキョロする全身黒ずくめの男の子、ロゴの入ったオリジナルサコッシュをぶら下げた女の子の姿がチラホラ見える。人波を器用にかきわけ目的の会場まで静かに歩く彼ら。ロゴの入ったリストバンドをしているので「MAZEUM」の参加者であることがすぐわかる。
最初はポツリポツリ……だが次第にその数は増え、とっぷりと日が暮れるとリストバンドを付けた彼らがいつのまにか町を占拠しているかのようにさえ見えた。イベント名の「MAZEUM」は“迷路”や“迷宮”という意味を持つMAZEと、“博物館”を意味するMUSEUMを合わせた言葉。京都の町中がまさしく“迷宮の博物館”に変わり、多くのギャラリーたちが集った瞬間がそこにあった。
改革と伝統が共存する町。誰もが認めるそんな京都の特徴は、音楽の歴史においても過去折に触れてその両サイドが切磋琢磨する形で現れてきた。個性的な大学が多いことから、ほかの地域から血気盛んな若い世代が移り住み新たなカルチャーを作っていく。例えば、村八分、裸のラリーズ、EP-4、非常階段、沖野修也、ローザ・ルクセンブルグ、竹村延和、rei harakami……彼らは皆そうした京都という強烈な磁力を持った土地で生命力を発揮した異才たちだ。そして、結果として彼らはメインストリームに対するカウンターとして今なお音楽史の中で不気味な(奇妙な?)存在感を放っている。なのにそこは、ふと見渡せば古い寺社仏閣がそこかしこにあり、優雅な川、背の低い山が身近にある風光明媚な場所。昨今では年間5000万人もの旅行客が訪れる世界的観光都市だ。
だが忘れてはいけないのは、お年寄りや子供も若者と一緒に生活する、つまり住民たちの日常がそこにあるということ。そこで普段通りの暮らしを営む人々が京都を京都たらしめてきた。京都にはクラブやライブハウスも多いが、その経営者や店長たちの多くは何よりまず京都の住民という意識が強い。“観光客のため”ではなく、そこに暮らす人々の目線で現場にいることが、ほかの町にはない特有の“音住接近”とでも言うべき音楽文化をサポートしてきたと言っていい。
「京都だからこそやる意味がある。東京では絶対にできない」
「MAZEUM」はそんな京都で、町中の寺やクラブを舞台にして開催された。初日である11月30日は、左京区は哲学の道の近くにある法然院という、谷崎潤一郎の墓もあることで知られる名刹と、京都きっての老舗クラブであるMETROが会場。2日目の12月1日は極楽寺、誓願寺、UrBANGUILD、OCTAVEという、いずれも繁華街ど真ん中にある4カ所が舞台となった。2日目の日中はこの4会場を使ってサーキット形式で行われた。
京都では毎年多くの音楽フェスやイベントが開催されていて、サーキット企画も決して珍しいものではない。だが出演者のラインナップをまずは見てほしい。まさに京都のカウンター音楽カルチャーの歴史を継承するかのような名前がズラリとそろっている。もちろん、この中で実際に京都で活動しているアーティストは数少ない。だが、キツネの嫁入りのリーダーであるマドナシ、船戸博史と渕上純子によるふちがみとふなと、MADEGGの活動名でも知られる小松千倫、2年前に東京から活動拠点を京都へ移して“外”というライブハウスをオープンさせた空間現代、DJとして活躍するPODDやTorei、そしてニューウェイブ全盛期の1980年代に京都で裏番長的存在だったEP-4の佐藤薫らが、他府県のみならず海外からも招かれた大勢の精鋭たちが並ぶ今回のタイムテーブルの中で、さりげなく鍵になっていることに気付かされる。
主催者の1人であり、そもそもの“言い出しっぺ”であるベルリン在住のライター / キュレーター / オーガナイザーの浅沼優子氏と開催数日前に話をする機会があったが、彼女は「町としての面白さ、歴史と新しさを併せ持つ京都だからこそやる意味がある。東京では絶対にできない」と断言していた。だからこそ、BLACK SMOKER RECORDSのJUBE、ベルベットサン・プロダクツのノイズ中村氏といった共に企画開催するスタッフも京都に何度も足を運び、フライヤーやポスター配布に奔走。開催2日前にはDOMMUNEでも特番を配信した。その甲斐もあって、フタを開けてみるとイベントは大盛況。この季節としては異例の温かさと好天に恵まれてその日を迎えることができたのである。
「MAZEUM」開演、フロアは満員に
初日は19:00に法然院で、スガダイローのライブからキックオフ。お堂に持ち込まれたグランドピアノに向き合った彼は、最低限の照明の下、ストイックに、しかしながらエネルギッシュに鍵盤を叩く。情熱的だが滑らかなフレーズが折り重なって高い天井に響きわたると、それはまるで「MAZEUM」の開催を高らかに宣言しているかのようだった。
そのあとは同じ法然院の大広間で、カリフォルニア大学の博士課程在籍中の女性電子音楽家、サラ・ダバーチの演奏がスタート。アンビエントに近い音のさざ波に、座布団に座った満員のオーディエンスが黙って身を任せる。室内は基本的に暗がり。その中で最後部からVJのRokapenisが窓越しに広がる庭園に向かって映像を映し出す。プロジェクションマッピングさながらの演出は見事に夜の東山の幻想を抽出させていた。
DJ NOBU、初来日となるカザフスタンのNazira、DJ HALとPWUによるツインDJユニット・halptribeが出演した深夜のMETROで朝5:00に初日を終えたあと、翌日2日目は日中からサーキットが開始。京都随一の繁華街である三条河原町交差点付近、河原町通を挟んで東西に位置する4カ所が会場だが、まずは極楽寺にて14:00から、PODD、和歌山出身の杉本戦車、キツネの嫁入りのマドナシ、ふちがみとふなとが次々に登場した。極楽寺は新京極通と河原町通の間の寺社密集地域、いわゆる裏寺と言われる場所の一角にある小ぢんまりとした寺だが、つぶやくような歌とラフな風合いのアコースティックギターでやさぐれた男の色気を伝えるマドナシの飄々としたパフォーマンスが、この会場の雰囲気にフィットした。
そのあとHIDENKAを挟んで登場したマヒトゥ・ザ・ピーポー(GEZAN)はこの日のハイライトの1つだったと言っていいだろう。ちょうど日も落ちてきた時間帯だったこともあり、時折犬の遠吠えのようにも聞こえる幻のような歌が、普段は亡き者たちの魂に祈りを捧げる場所である寺の空気に見事に溶け込んでいた。
極楽寺から少し遅れて15:30頃にはOCTAVEとUrBANGUILDでもライブがスタートした。この2つの会場は高瀬川を挟んで目と鼻の先の近さ。UrBANGUILDでテンテンコがライブの口火を切ると、OCTAVEでは先陣を切っていたBomb birds ya!に続いて食品まつり a.k.a foodmanが登場する。かと思えば、UrBANGUILDではKOPY、DJ SOYBEANSと続き、OCTAVEではKen FURUDATE、フロアから離れて厨房近くで蛍光灯テルミンを操る様子が斬新だったANTIBODIES Collectiveが間断なく現れ、それに応じてオーディエンスの動きもたちまち慌ただしくなる。
UrBANGUILDがこの日最初のピークを見せたのは18:00前後、テンテンコと伊東篤宏によるユニット・ZVIZMOにcontact Gonzoが加わった瞬間だった。組み体操のようなcontact Gonzoのパフォーマンスは、フィジカルではあるが一方で示唆的な現代芸術のよう。さらにZVIZMOによる強烈でポップなノイズがその肉感的な動きに拍車をかける。ほぼ同じ時刻にOCTAVEでは、小松千倫から空間現代 feat. THE LEFTYにつながる強力な流れが場内を熱くしていた。後ろからではもはやステージで空間現代の3人がどういう立ち位置で演奏しているのか見えないくらいにフロアは満員に膨れ上がっていたが、KILLER BONGとJUBEというBLACK SMOKERの中心人物2人のユニット・THE LEFTYがオーディエンスを扇動させているのは伝わってくる。畳みかけるようでいて、間をしっかり取りながらシャープで重厚なアンサンブルを作り出す空間現代は、地域性においても音楽性においても、あらゆる点でハブになる重要な存在であることを痛感させられた。
OCTAVEはDJ YAZIのプレイを経て、オーラスとしてアメリカでも高い評価を得ているエクストリームミュージック&ブラックメタル系バンド・ENDONが登場し大団円に。一方で、もともとは京都で活動していたというAMAによる手作りカレー、ベーグル、スイーツなども飛ぶように売れていた。ハードで男臭い匂いとハンドメイドの親しみやすさが一体となったOCTAVEの空気は、その後24:00からの部にも引き継がれていった。
首謀者たちはすでに次回開催に向けて夢を膨らませている
その頃UrBANGUILDでは、ToreiのDJに続いて現れたベテラン佐藤薫と、その佐藤が現在主として活動するEP-4[fn.ψ]が轟音ノイズを響きわたらせていた。EP-4の首謀者として1970年代から関西と京都のアンダーグラウンドシーンを支えてきた生き証人的存在の、今回の出演者ではおそらく最年長であろう佐藤。彼は今回ソロパフォーマンスからライブを開始し、PARAなどで活躍する家口成樹とのユニット・EP-4[fn.ψ]へとシームレスにつなげる構成で、力技ではない、むしろ柔とも言えるノイズのボディブロウを披露していた。
その佐藤とほぼ同時刻に最後の会場である誓願寺でもパフォーマンスがスタート。ここでライブを行ったのは全身音楽家とも言える山川冬樹、そして志人(降神)×スガダイローという2組だけだったが、共に入場規制がかかるほどの大盛況となった。この誓願寺の2組だけでも独立したイベントになりそうなくらい創作性が高く、示唆に富んだ組み合わせゆえに、最初からこの2組の観覧を目的にチケットを確保していたファンも多かったそうだ。
そしてUrBANGUILDでのもう1つのピークはGOATと、その志を受けるかのようにすぐさま始まった行松陽介の鮮やかなバトンパスだったろう。日野浩志郎を中心としたGOATは、現在メンバーの居住地が東西に別れていることもあり、なかなか頻繁にライブができなくなっている。大阪を拠点にYPYとして活動することが多い日野だが、この日はGOATとしては2018年に入って初めての関西での公演。当然のように始まる頃には会場入り口までギッシリ満員だ。冒頭から中盤にかけてはシロフォンやマリンバをメンバー4人で囲うように演奏。ポリリズミックに音を錯綜させる様子は、手元がよく見えない状態であっても観ているほうも手に汗を握るほどだ。日野に至っては終始背中を向けたままだったが、あくまで打楽器だけでここまで大きなグルーヴを創出させることができることに驚かされる。そして後半は、日野はベースを弾いているものの比較的通常のGOATに近いバンド編成でライブを実施。鋭い切り返しを生かした、知的かつ身体性の高い演奏を見せつける。サックス、ドラム、パーカッション、そしてベース。いずれもコチコチに音をミュートさせているのに、どうしてこんなにしなやかなのだろう。フィニッシュに至るまでの細やかかつ大胆な展開は鮮やかと言うしかなく、最後にビシッと音が止まったときの震えが来るような瞬間、そしてそこからホットな空気が冷めやらぬうちに始まった行松のアグレッシブなパフォーマンス、これこそ「MAZEUM」最大の山場でもあったと言える。
24:00に再びOCTAVEが開場し、GAJIROH & RACYや、アメリカのムーア・マザー、BLACK SMOKERS、THE OTOGIBANASHI'SのBIM、YOTTUらが出演。昼間とは異なる、アンダーグラウンドヒップホップ色の強いエッジーなオーディエンスが集う様子も壮観だった。
主催者による公式発表によると2日間の有料入場者数は約800人で、アーティスト仲間や関係者を含めると1000人は軽く超えたという。「200人来てもらえれば……」などと事前に不安視していた主催者たちだったが、これはもう予想をはるかに超える大成功と言っていい。首謀者たちはすでに次回開催に向けて夢を膨らませている。間違いなく第2回目、第3回目もある。そんな確信を残し、手探りで始まったかに見えたこの“迷宮の博物館”の1stステージは幕を閉じた。
取材・文 / 岡村詩野

関連記事

GEZANの100時間ライブ全貌公開!ゲストに下津光史、スチャBose、中村達也、後藤正文ら

「ARABAKI」第3弾発表でアレキ、エルレ、くるり、スカパラ、モンパチ、優里、礼賛ら13組

GEZANが計100時間ぶっ続けでライブ、走り切った瞬間にアルバムリリース

GEZAN新アルバム「I KNOW HOW NOW」の収録曲発表、青葉市子らゲスト参加
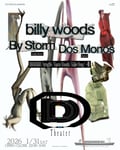
Dos Monos主催「Theater D」の追加出演者発表、没によるステートメントも

GEZANの47都道府県ツアー「集炎」岡山公演映像を今夜YouTube公開、撮影・編集はヴィンセント・ムーン

GEZANニューアルバム「I KNOW HOW NOW」発売、先行シングル「数字」MV公開

MSC「MATADOR」「帝都崩壊」アナログ盤リリース、今も語り継がれる2000年代の名盤

ENDON、約40分のラストライブ映像がYouTubeで公開 大石規湖監督が制作



