細野晴臣が生み出してきた作品やリスナー遍歴を通じてそのキャリアを改めて掘り下げるべく、さまざまなジャンルについて探求する「細野ゼミ」。2020年10月の始動以来、「アンビエントミュージック」「映画音楽」「ロック」など全10コマにわたってさまざまな音楽を取り上げてきたが、細野の音楽観をより深く学ぶべく2023年より“補講”を開講している。
ゼミ生として参加するのは、氏を敬愛してやまない安部勇磨(never young beach)とハマ・オカモト(OKAMOTO'S)という同世代アーティスト2人。今回は番外編として、6月25日に発売50周年を迎えた氏の2ndソロアルバム「トロピカル・ダンディー」をフィーチャーする。「HOSONO HOUSE」とは趣を異にする独自の音楽性が表現された本作は、どのような環境やマインドで作られたのか。安部とハマが迫る。
取材・文 / 加藤一陽 題字 / 細野晴臣 イラスト / 死後くん
四畳半の部屋で生まれた「トロピカル・ダンディー」
──細野さんが1975年に発表したソロ2作目「トロピカル・ダンディー」が発売50周年を迎えました。それを記念して、今回は「トロピカル・ダンディー」をテーマに進めていければと思います。
安部勇磨 このジャケットって、細野さんもデザインのアイデアを出したりしてるんですか?
細野晴臣 いやいや、「トロピカル・ダンディー」というイメージでイラストレーターの八木康夫(ヤギヤスオ)さんに頼んだらすぐ返って来て。それを見て、即決だったな。
ハマ・オカモト 何か元ネタはあるんですか?
細野 イギリスの「NAVY CUT」っていうタバコの箱のデザインがモチーフになってる。輪っかの中に水兵がいるんだよ。僕は当時「ハイライト」を吸っていたんだけど、「ハイライト」じゃサマにならない。
ハマ 「HOSONO HOUSE」とは録音環境も全然違いますよね。
細野 全然違う。「HOSONO HOUSE」ははっぴいえんどの流れで作った作品だから、吉野金次さんにミックスしてもらったり、制作スタッフも同じで。でも、「トロピカル・ダンディー」は赤坂にあったクラウンのスタジオで録ったんだよ。そこにあったミキシングコンソールを見て、「なんてイナたい卓だろう」と思って。イギリスのTridentのコンソールだったんだけど、何をやったって味わいのある音になる。その卓のよさを積極的に生かして作ったのが、次の「泰安洋行」。「トロピカル・ダンディー」のときは初めて使うから、「へえ」って感じだった。
──曲作りを始めたのは、どのくらいから?
細野 埼玉の狭山に住んでるときに「HOSONO HOUSE」を作って。その後、娘が産まれるというので、病院の近くの西落合にアパートを借りて1年くらい住んだんだよ。その時期に「トロピカル・ダンディー」を作ったんだよね。四畳半の部屋で。
ハマ ベースラインやシンセのフレーズも、ある程度、細野さんが考えたんですか?
細野 どうだったけな。「泰安洋行」はけっこうきっちり作っていったけど、この作品は思いつきで作ったんで。ミュージシャンの人たちに任せる感じ。
ハマ それにしては、すごく完成されてますよね、アレンジとか。デモはアコギで作っていたんですか?
細野 そうね。けっこうアコギで作ってたね。あと、自分の部屋にエレクトリックピアノがあって、それがすごい好きだった。ただ、使いすぎて鍵盤が折れちゃったんだよ(笑)。
ハマ 鍵盤が折れるって聞いたことない(笑)。先ほど一緒に録音されるミュージシャンの人に任せるとおっしゃっていましたけど、とはいえ、きっと細野さんの頭の中に鳴っている音もあるじゃないですか。
細野 頭の中では、わりとカリブっぽい音が鳴ってた。マイティ・スパロウとかね。あとはヴァン・ダイク・パークスの影響が強かったよね。最初に考えついたのがマイティ・スパロウのようなサウンドだった。バイヨンの「♪チャーチャ、チャーチャカ」ってリズム。それで「北京ダック」という曲ができた。そこで満足しちゃったんだけど、1曲じゃダメだろうと思って、でっち上げていろいろ作って(笑)。なんとかA面をコンセプト通りに作って、それで力尽きたのでB面をおまけで作ったんだね。あり物の曲を使ったりして。
安部 「北京ダック」が最初にできたんだ。
細野 うん。でも、そのちょっと前までは、Little Featとか、ビリー・プレストンとかを聴いてたわけでしょ。ベーシストとしてはファンクが好きだったから、レコーディングの1テイク目はファンクの曲を録音したんだよ。「北京ダック」のレコーディングの1週間くらい前かな。でも、ファンクのリズムだとどうしても歌えないんだよ。ファンクは僕の歌と合わない(笑)。それでストップさせちゃったんだよね。
ハマ もしそれで細野さんが納得いく録音ができていたら、違うテンションのアルバムができていたかもしれないですよね。
細野 僕が歌えていたら、いまだにファンクをやっていたかもしれない。ビリー・プレストンをレコーディングメンバーみんな聴いていて、かなり影響されてるんだよね。今聴くとどうなんだか知らないけど、当時は斬新だったから。だからそういうアルバムを作ろうと思ったんだけど、挫折して。で、どうしようかちょっと考えていたところに久保田麻琴がやって来て、「細野さんはトロピカルダンディーだ」と言ったんだよ(笑)。それで、一発でアルバムのイメージが決まったわけ。
ハマ 伝説のひと言が。その言葉、発明ですよね。めちゃくちゃわかるけど、よくぞその言葉が出ました、ですよ。細野さんは、その言葉を気に入ったんですか?
細野 いいなと思ったんだよね。
──久保田さんは何をもって細野さんのことを「トロピカル」と表現したんでしょうね。
安部 何かを感じたからそう言ったわけですもんね。
細野 それがわかんないんだよね。顔かな(笑)。本人もなんでそう言ったのかわからないみたいだけど。直観的に言ったんだろうね。
久保田麻琴のひと言で路線変更
ハマ 話を戻すと、前段としてファンキー路線のティン・パン・アレーのテンションがあったんですね。
安部 アルバムに入ってないファンク路線の曲もあったんですか?
細野 あったよ。1曲だけ、アレンジを変えて「フィルハーモニー」に入れたんだよ。「L.D.K.」という曲なんだけど。でも、あんまりうまくいかなかった(笑)。
安部 へえ!
細野 The Watts 103rd Street Rhythm Bandとか、あのへんのバンドに影響を受けていてね。彼らのやり方に影響されていたかも。まあ、そんな感じでファンクが好きだったんで、もし歌えてたり、自分のソロを作らなかったら、ミュージシャンとしてそっちに行っちゃってたね。ハマくんみたいに。
ハマ すごい話だな。トロピカル路線に向かう転機。
細野 1日で変わったという。分かれ道だよ。久保田くんのひと言で全部そっちに行っちゃった。アルバムでカルメン・ミランダの「Chattanooga Choo Choo」をカバーしてるんだけど、演奏はLittle Featみたいなんだよね。スライドギターが入っていたり。オリジナルの雰囲気とは違うけど、「まあいいや、これが今の自分だろう」と思って。
キーパーソンは佐藤博
ハマ バンドの皆さんの適応力もすごいですよね。この間までファンキーな曲を演奏していたのに、急に「北京ダック」のデモができあがってきたときに、「あっ、この感じね」ってわかり合える。その感度が恐ろしい。
安部 でもどうなんだろう。実際、みんな同じような感度だったんですか? びっくりして「何これ!?」ってならなかったんですか?
細野 たぶん、びっくりしてたと思うよ(笑)。
安部 そういうときって、どう演奏していいかわからなくなると思うんだけど。
細野 彼らの手法はロックやファンクだから、基本的にはそういう音になるわけだよね。当時、僕とバンドメンバーの仲介役だったのが、キーボード奏者の佐藤博だったんだ。彼は大阪にいた頃、クラブに出ていてエキストラをやったり箱バンみたいなジャズバンドに入ったり、いろいろアルバイトしてたわけ。だからいろんな音楽を知ってたんだよね。いろんなことに対応できるオールマイティなプレイヤーだったんで、「北京ダック」のデモを聞かせたときにクラビネットを弾いてくれて、そのフレーズがよかったんだよ。「このフレーズがあれば、この曲はいけるな」と。
ハマ あのフレーズ、佐藤さんが「こんなんどう?」って感じで出したってことですか?
細野 そう。佐藤博の存在はすごく重要だったね。
ハマ スタジオで一緒にやるミュージシャンに任せていたというのはそういうことですよね。細野さんがフレーズを指定してたわけじゃない。
安部 あのー……お金の話になっちゃうんですけど。
ハマ 突然(笑)。
安部 ミュージシャンの皆さんをスタジオに呼ぶじゃないですか。そういうときって、“1日何時間拘束でいくら”みたいなギャラの規定はあったんですか? 1カ月やるとなると、今の僕らの感覚だと、なかなかね。
細野 ミュージシャンをインペグする場合はそうだけど、僕らはバンドスタイルだったんで。トータルでギャラが出てると思うけど、そこには全然タッチしてないからわからないな。キャラメル・ママというバンドだったから。ただ松任谷(正隆)くんはこのときはいないんだよね。
ハマ 正確には、キャラメル・ママとちょっと違う。佐藤博さんとかも含めたメンバー。
伝説の中華街ライブの舞台裏
安部 「北京ダック」の歌詞が大好きなんですけど、どんな世界観を想像してこんな歌詞が生まれたんだろう。そのとき読んでいた本の影響とか?
細野 藤子不二雄Aの短編マンガだよ。北京ダックなんとか……っていうタイトルの(「北京填鴨式」)。
安部 横浜を舞台にしたのは?
細野 よく遊びに行ってたんで。遊ぶと言っても、フラフラしてるだけ。姉に連れられて、元町とかに小学生の頃から行ってたんだよ。そこでしか売ってないトレーナーを買ったりして。FUKUZOっていうブランドだったね。中華街で火事が起こるという歌を歌っているのに、同發新館というレストランでライブをやらせてもらって、中華街の人からひと言も文句を言われなかったんだよ。「いいのかな?」と思っていたんだけど。
ハマ のちに(星野)源さんをゲストに呼んでそのライブの再現公演をやられていましたけど(参照:細野晴臣40年ぶり中華街ライブで星野源とゲロッパ!)、オリジナルのライブもすごいですよね。ちょっと脱線しちゃいますけど、あのライブはなんで映像を収録したんですか?
細野 あれは景山民夫(放送作家、小説家)の存在があってこそできたテレビ番組。
ハマ うっわ、テレビだったんだ!
細野 クラウンの要望で、クラウンから派遣されたカメラで違うフィルムでも撮ってる。今みんなが観てるのはそっちのほうで、テレビ番組の映像は残ってないんだよ。観たいんだけどね。どこかに残ってないかな。
安部 ……あれをどんだけ真似したいと思ったことか。
ハマ 本当に。あの衣装もね。
細野 あの衣装は自前だね。
安部 細野さんから、メンバーの皆さんに衣装の方向性を説明するんですか? 「こんな雰囲気だよ」みたいな。言い方アレだけど、うさん臭さ、怪しさみたいな(笑)。
ハマ 細野さんの格好がキマってるから余計ね、周りのみんなも(笑)。
細野 あの時期には、みんなもわかってきたから、この世界を。景山くんもわかっていたしね。
安部 あの緊張感のある中、演奏のギャップがすごいカッコよくて。
ハマ お客さんからも近いしね。本当に生音みたいな状況だし。
細野 長門芳郎くんという当時のマネージャーがステージ周りのセットを考えてくれた。
ハマ 細野さんが着ている、あの印象的なスーツは?
細野 中古の麻のスーツみたいな。よく覚えてないんだけど。
安部 あの時代、皆さん恰好がいいんだよね!
ハマ そもそもあの時代に作られた洋服のカッコよさのポテンシャルもある。あのとき、細野さんがちょっとフレームの角数が多い眼鏡をかけてらして。それを観て、僕、そういう形の眼鏡をかけ始めたんですよ。それまで黒縁だったのに。あの映像を何度も一時停止して。「これ、何角形なんだろう」って。
安部 僕も「細野晴臣 時計」とかで検索したことがあります。
細野 最近になって、そういうことを言われることが増えた。「靴がなんとかだ」とかね。SNSでそういうコメントを見て、みんなそういうところを見てるんだということを知ったよ。だからうかうかしてらんないよ。
ハマ やっぱりファンとしては、中華街ライブの映像があるっていうのはすごいことだと思いますよ。
細野 でもね。恥ずかしいんだよね。炭酸飲料を飲みすぎて歯がボロボロなんだよ。
ハマ それ、親が子供に止めさせるための理由じゃないですか(笑)。
細野 家の真向かいに親戚が住んでいたんだけど、大使館か何かに勤めていて、洋物をいっぱい持ってるわけ。
ハマ 洋物(笑)。
細野 日本でまだ売ってなかった時代だったんだけど、親戚の家に行くとそれを飲まされるんだよ。初めは「薬みたい」って思ったんだけど、だんだんクセになってきて。だから中華街ライブのときは歯が抜けたりしている。「歯が抜けたまま歌ってる人って、今まで2人しか見たことない」ってピーター・バラカンに言われたよ。もう1人はイギリスのThe Special AKAの人(ジェリー・ダマーズ)(笑)。今思うと恥ずかしい。やっと今、普通の人間になったよ(笑)。
安部 この連載、こういう話が聞けるのが大好き(笑)。それがむしろ音楽の面白さというか、危うさにつながってる感じがしていいなって。
ハマ このエピソードも、場合によっては松田優作が役作りで奥歯を抜いたみたいなことと同じように語られるというか(笑)。真似する人がいたっておかしくない。
細野 真似しないように(笑)。
<後編に続く>
プロフィール
細野晴臣
1947年生まれ、東京出身の音楽家。エイプリル・フールのベーシストとしてデビューし、1970年に大瀧詠一、松本隆、鈴木茂とはっぴいえんどを結成する。1973年よりソロ活動を開始。同時に林立夫、松任谷正隆らとティン・パン・アレーを始動させ、荒井由実などさまざまなアーティストのプロデュースも行う。1978年に高橋幸宏、坂本龍一とYellow Magic Orchestra(YMO)を結成した一方、松田聖子、山下久美子らへの楽曲提供も数多く、プロデューサー / レーベル主宰者としても活躍する。YMO“散開”後は、ワールドミュージック、アンビエントミュージックを探求しつつ、作曲・プロデュースなど多岐にわたり活動。2018年には是枝裕和監督の映画「万引き家族」の劇伴を手がけ、同作で「第42回日本アカデミー賞」最優秀音楽賞を受賞した。2019年3月に1stソロアルバム「HOSONO HOUSE」を自ら再構築したアルバム「HOCHONO HOUSE」を発表。この年、音楽活動50周年を迎えた。2023年5月に1stソロアルバム「HOSONO HOUSE」が発売50周年を迎え、アナログ盤が再発された。2024年より活動55周年プロジェクトを展開中。2025年6月に2ndソロアルバム「トロピカル・ダンディー」のアナログ盤が再発された。
安部勇磨
1990年東京生まれ。2014年に結成されたnever young beachのボーカリスト兼ギタリスト。2015年5月に1stアルバム「YASHINOKI HOUSE」を発表し、7月には「FUJI ROCK FESTIVAL '15」に初出演。2016年に2ndアルバム「fam fam」をリリースし、各地のフェスやライブイベントに参加した。2017年にSPEEDSTAR RECORDSよりメジャーデビューアルバム「A GOOD TIME」を発表。日本のみならず、アジア圏内でライブ活動も行い、海外での活動の場を広げている。2021年6月に自身初となるソロアルバム「Fantasia」を自主レーベル・Thaian Recordsより発表。2024年11月に2ndソロアルバム「Hotel New Yuma」をリリースし、初の北米ツアーを行った。never young beachとしては2025年12月8日に初の東京・日本武道館公演を行う。
ハマ・オカモト
1991年東京生まれ。ロックバンドOKAMOTO'Sのベーシスト。中学生の頃にバンド活動を開始し、同級生とともにOKAMOTO'Sを結成。2010年5月に1stアルバム「10'S」を発表する。デビュー当時より国内外で精力的にライブ活動を展開しており、2023年1月にメンバーコラボレーションをテーマにしたアルバム「Flowers」を発表。2025年2月に10枚目のアルバム「4EVER」をリリースした。またベーシストとしてさまざまなミュージシャンのサポートをすることも多く、2020年5月にはムック本「BASS MAGAZINE SPECIAL FEATURE SERIES『2009-2019“ハマ・オカモト”とはなんだったのか?』」を上梓した。

関連記事

静岡「FUJI & SUN '26」第1弾で柴田聡子、Chappo、チョコパ、寺尾紗穂、ネバヤン、ハンバート
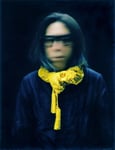
藤原ヒロシ流ラヴァーズロック「KOTOBA」配信開始、渡辺シュンスケやスカパラのメンバー参加

細野晴臣が20世紀を経て向かう先

細野晴臣のレコードがずらり!神保町の一角にオープンした「Hosono Record House」に行ってみた

細野晴臣が20年前に再び歌い始めた理由

never young beach、初の日本武道館公演で結成10周年を締めくくる
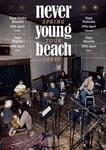
never young beach、4月に4都市Zeppツアー開催

KEIJUぴあアリーナワンマンにKID FRESINO、OKAMOTO'S、BIM、guca owl

&TEAM「沼にハマってきいてみた」に登場、韓国デビューにカメラが密着



