お笑い芸人たちがさまざまなオリジナルソングを真剣にパフォーマンスする、テレビ東京の深夜バラエティ番組「ゴッドタン」の人気企画「芸人マジ歌選手権」。この企画に参戦する並み居る芸人たちに混じり、東京03の角田晃広率いる「角田バンド」でベースや鍵盤を演奏しているのが“大竹マネージャー”こと大竹涼太氏だ。プロダクション人力舎で山崎弘也(アンタッチャブル)、ゆってぃなどのマネージャーを務め、ASH&Dコーポレーションに移ってからは阿佐ヶ谷姉妹やラブレターズなどを担当。「アメトーーク!」の「マネージャーと二人三脚芸人」の回に阿佐ヶ谷姉妹と一緒に出演していた大竹氏だが、物静かながら存在感のある佇まいに「この人はいったい何者なんだろう?」と気になっている方も多いのではないだろうか。
「アメトーーク!」で「『きしたかの高野の喉爆発ライブ』に行きたくて仕事を調整した」と語っていた通り、芸人のマネージャーであると同時に1人のお笑い好きである大竹氏は、同様にnhhmbaseの再結成ライブがどうしても観たくて阿佐ヶ谷姉妹のテレビ収録現場を抜け出したほどの音楽好きでもある。そんな大竹氏のこれまでの遍歴とともに、本連載のテーマである音楽とお笑いの関わりについて考察を聞こうと取材をオファーしたところ、「音楽とお笑いの蜜月」を説く過去回を読んだ彼から「そもそも音楽とお笑いは対等ではなく、対立した緊張関係にあるのではないか」という思いもよらぬ一石が投じられた。この記事では音楽とお笑い、両現場の裏側を知る大竹氏が考える音楽とお笑いの関係について紐解いていく。
取材・文 / 張江浩司 撮影 / つぼいひろこ
音楽とお笑いは完成地点が違う
この連載は始まったとき(参照:「おんがく と おわらい」第1回 漫才の誕生、コミックバンド、テレビバラエティ……音楽とお笑いの蜜月)から注目していました。特に1回目は壮大な物語があってすごいなと。今回呼んでもらって光栄です。
──ありがとうございます。こちらこそ、音楽もお笑いも大好きで、裏方としての俯瞰した目線を持っている大竹さんの考えはぜひ聞いてみたいと思っていました。取材にあたって大竹さんからは事前に「音楽とお笑いの関係は本当にうまくいっているのか? むしろ、対立・緊張関係にあるのではないか」という大変興味深いテーマを投げかけていただきました。
オファーをいただいてからの1カ月、ずっとこのテーマについて考えていて(笑)。いろいろ考えてみても、やっぱり音楽とお笑いはうまく融合していないと思うんです。
──この連載の第1回で書いたように、音楽とお笑いは文化的に近い起源があったとしても、現状はそうではない?
そうですね。お笑いが音楽を取り入れてうまくいっているケースは多いと思うんですけど、その逆はあまりないんですよね。
──なるほど。「お笑いが音楽を取り入れるケース」と「音楽がお笑いを取り入れるケース」は分けて考えなければいけないと。
はい。そういう意味で対等じゃないと思うんです。
──確かに「音楽的な要素を取り入れたお笑い」は「歌ネタ」「リズムネタ」という言葉があるくらいですし、楽器を使う芸人さんも多いです。「お笑いの要素が入っている音楽」だと、例えば岡崎体育さんの「MUSIC VIDEO」はどうですか? いわゆる“あるある”の手法ですよね。
僕も岡崎体育さんは真っ先に思い浮かびました。でも、岡崎体育さんの作品の中に「そういう曲もある」というだけで、岡崎さんもお笑いの要素がある音楽だけをやっているわけじゃないし、やっぱり圧倒的に少ないんですよ。僕なりになぜ対等じゃないのかという理由を考えてみたんですけど、「表現としてどの時点で完成とするか」が違うからじゃないかと思うんです。
──“完成”ですか?
音楽はどんな変な曲でも、ミュージシャンが演奏して、聴いている人の耳に入った時点で完成だと思うんです。聴いている人がその曲で感動しても、不愉快になっても、聴かれたらそこで終わり。でも、お笑いは客前でネタをやって、ウケたところで完成なんじゃないか。ウケなかったらそれは未完成なものとして、価値がなくなってしまう。ウケないネタにも音楽と同じように価値があるという意見の人もいるかもしれないけど、「客が笑うか」という絶対的な評価軸が存在しているんですね。
──なるほど! ミュージシャンがインタビューで「この曲の解釈はリスナーに委ねます」と言っていることがありますけど、それは芸人だとありえないわけですね。「このネタはお客さんに委ねます」とはならない。
音楽にはその余裕というか、裾野の広さがあるから、誰が歌って演奏しても“音楽になる”と思うんです。歌がうまいとか下手とか、そういうことを抜きにしても成立するというか。でも、お笑いは「お客さんを笑わせる」というゴールが決まっている。お客さんの反応をコントロールしたい文化なんじゃないかと思うんです。捉え方によっては、お笑いのほうが傲慢なエンタテインメントではありますよね。
──「面白かったら笑うんですよ」という強制力が働いている。
そうです。音楽はリスナーの反応までコントロールできないですから。ライブでも、観客は盛り上がって腕を振り上げてもいいし、踊ってもいいし、黙って聴いてもいい。岡崎体育さんの「MUSIC VIDEO」も、笑ってもいいし、「曲がいい」と思ってもいい。表現する側が受け手の評価にはタッチしないんですよね。その違いがあると思うんです。
──根本的に目指しているところが違うというか。
そうかもしれないです。昔、すごく小さなライブハウスに灰野敬二さんを観にいったことがあるんですけど、たまたま最前列の席で、目の前で灰野さんが叫びまくっていて(笑)。あまりの迫力に僕は背筋を伸ばして声も出せない状態だったんですけど、一生忘れられないくらいうれしい体験でした。
──歓声が上げられないくらいすごい音楽ライブってありますもんね。一方で、“笑い声が上げられないくらい面白いお笑いライブ”は基本的にはないと。
今はなくなっちゃったんですけど、銭湯の2階に下北ファインホールという非常階段を乗り越えてやっと到達できる狭い小劇場があって。そこに西口プロレスの芸人さんたちが主催していたイベントを観に行ったんです。狭すぎて壁に張り付くようにして観たんですけど、東京ペールワンの漫才がめちゃくちゃ面白くて、みんなものすごく笑っていました。
──アンダーグラウンドな現場で披露されるエキセントリックなネタでも、やっぱり笑い声が上がるんですね。音楽のようにパフォーマンスに圧倒されて黙ってしまうとはならない。
みんなで笑う心地よさもあるのかもしれません。
「マジ歌」で繰り広げられる音楽とお笑いのマジゲンカ
「マジ歌選手権」は、基本的にすべてお笑いの文脈で作られているんですね。どんなにいい曲でも、観ている人が笑わないと成立しないんです。なので、「このメロディのほうが笑いやすい」とか「ここは16小節に伸ばしてセリフを入れて、オチのひと言の前でブレイクしましょう」とか、そういうふうに作っていくので、100%お笑い優先。音楽が蔑ろにされていると言ってもいいくらいかもしれない。
──音楽がお笑いのための道具になっている状態ですね。
ただ、マジ歌のすごいところは、直前まで完全にお笑いのやり方でお客さんの笑い声をコントロールするために作っているのに、いざ本番になると音楽がお笑いを食い破ってくることがあるんですよ。
──食い破る?
音楽の感動がお笑いを上回って、スタッフさんもお客さんも、本当に曲を聴いて感動させられた顔をしているときがあるんですよ。僕も僕で、デカいライブを終えたバンドマンの顔になっているんですけど(笑)。お笑いのメソッドで緻密に作られた曲だけど、最終的に音楽的な感動が凌駕するのか、笑わせるという目的で反応をコントロールしきるのか。お笑いと音楽、どっちが勝つのか。実はそういうスリリングさがマジ歌の醍醐味だと思っているんです。
──音楽とお笑いの融合ではなく、胸ぐらをつかみ合うケンカだと。
角田バンドがマジ歌のイベントで必ず演奏する「ココロノハコ」という曲があって。一度聴いたらオチの歌詞もバレてるし、お笑いとしてのインパクトは弱くなっているんですけど、みんな何度も聴きたくなっちゃってるから毎回やるっていう(笑)。
──完全にアンセムと化してる(笑)。
この曲は「ゴッドタン」のカメラマン・風間(誠)さんが角田バンドにドラマーとして参加することになって、初めてバンド編成で作った曲なんです。角田さんがサビに持ってきたコードが「G→D7→Em」で、僕はこれを「角田進行」って呼んでるんですけど(笑)、このコード進行が初めて登場したのが「ココロノハコ」でした。熱いコード進行なんですね。角田さんも無意識に気合いが入ってたのかな。それまでの人生が必然的に選ばせたコード進行のように思います。 僕はGEZANというバンドが好きなのですが、GEZANのマヒト(マヒトゥ・ザ・ピーポー)さんが、ドラムのシャーク安江さんが脱退したタイミングのインタビューで「次に出す曲は名曲になることが義務付けられてる」というようなことをおっしゃっていて、そして新ドラマーの石原ロスカルさんが加入後に出したのが「Absolutely Imagination」という名曲だったんです。僕は勝手に角田バンドとGEZANをリンクさせてるんですけど、「うわ! 僕たちと一緒だ!」と思って(笑)。「ココロノハコ」は角田バンドの「Absolutely Imagination」なんです。
──披露する前から名曲になることが決まっていたという。
歌詞が先にできあがって、リハーサルスタジオでアレンジを詰めていたときはまだ全然お笑いのロジックだったんですよ。風間さんのインパクトを強めたいからドラムソロで入るのがいいんじゃないかと話しながら進めていたのに、いつの間にか全員一斉に弾き出すアレンジになって、だんだんバンド感が出てきて(笑)。いざ本番のときに、風間さんがリハの4倍くらいの強さでハイハットを叩いてカウントしているのを聴いたらもう、全員の心が音楽に飲まれました(笑)。審査員の芸人さんもゲストも皆さん総立ちになって拍手してくれましたし。
──音楽がお笑いのコントロール力を凌駕した瞬間ですね。
芸人さんは“お客さんを笑わせる”というルールでずっとやっているので、その場を笑いでコントロールする力はものすごいんですよ。僕が言うと失礼になってしまいますけど、例えば日村(勇紀 / バナナマン)さんのマジ歌は、ヒム子が音楽に勝ってると思うんです。ヒャダインさんとか玉屋2060%(Wienners)さんが作ったハイクオリティな曲を、日村さんがお笑い力でねじ伏せているというか。
──確かに、あれだけキャッチーかつトリッキーな曲なのに、ヒム子のシルエットがまず頭に浮かびます(笑)。とんでもなく高いレベルでの攻防になっていますね。
芸人やスタッフ、作家さんが作った分厚いお笑いの壁を、たまに音楽が突き破っちゃうから面白いんだと思います。
──そう考えると、音楽にお笑いのエッセンスを入れると、リスナーに自由な解釈が委ねられてるところに“笑う”という正解が設定されることになり、あまりうまくいかないのかもしれません。
そうですね。窮屈に感じるのかもしれない。
──逆にお笑いの中に不確定要素として音楽が入ると、マジ歌みたいにスリリングになる可能性があると。大竹さんはマジ歌に音楽側の人間として参加していますよね?
確かに、音楽代表としてステージに立っているかもしれません(笑)。
──2018年のイベント「マジ歌ライブ2018 in 横浜アリーナ~今夜一発いくかい?~」では大竹さんが演奏後にベースを高く投げていたのが印象的でした(参照:ハライチ、2人揃ってAMEMIYAに「うるせー!」マジ歌ライブin横アリに1万2000人)。
演奏するだけが音楽じゃないというか、足踏み1つ、腕の振り1つもパフォーマンスであり、音楽じゃないですか。まあ、演奏してるうちに熱くなって全力でやっちゃいますね(笑)。
音楽は無頓着、お笑いは傲慢
──観客をコントロールしたいお笑いと、聴き手に評価を委ねたい音楽。それぞれの目指すところが違うということがだいぶわかってきました。
まったくの初心者でも聴いてる人の心を何か動かせたら音楽になるから、音楽は懐が深いですよね。でも、その崇高性に甘えて、お客さんを楽しませることに対して無頓着なミュージシャンも多いというか。MCもせずに「ボーカルの人が黙って水飲んでるのを見る、この時間、なに?」っていう(笑)。一方、お笑いはお笑いで、さっきも言ったように傲慢なところがあるので。
──音楽とお笑いを組み合わせて面白いものを作るには両者の緊張関係が必要だと。馴れ合ってはダメなんですね。
すごくダサいバラエティみたいになっちゃうと思うんですよ。音楽にもお笑いにも失礼というか。
──今ふと思ったんですけど、トリプルファイヤーは歌詞も、ボーカルの吉田(靖直)さんの佇まいも面白いじゃないですか。
面白いですよね。僕は「ブラッドピット」という曲の歌詞が一番好きです。
──あのバンドも、メンバー全員が「笑える音楽やってます!」みたいなスタンスだったら面白く感じられないと思うんです。バンド自体が音楽とお笑いの緊張関係を内包しているというか。吉田さん自身の中にも相剋がありそうですし。奇跡的なバランスのバンドのような気がしてきました。
なるほど、そうかもしれません。演奏もえげつないくらいタイトでカッコいいですもんね。
忘れられない永野の爆音ネタ
──ここまでの話とズレてしまうかもしれないのですが、音楽とお笑いが同じ方向を向いていた時代もあるように思うんです。「ポップミュージックはお客さんを踊らせて笑顔にさせてなんぼだよね」という、機能的な側面が重要視されていた時代というか。それだと音楽とお笑いを無理なく融合できたし、クレージーキャッツはその結晶なんじゃないかと。少々乱暴なまとめ方をすれば、クレージーキャッツ以降にポップミュージックが多様になって、「客を楽しませるだけじゃないぞ」というパンク的というかアンダーグラウンド的な価値観が生まれて、それが徐々に広まっていったのではないか。一方お笑いは、最近「地下芸人」という言葉も広がりましたし、もしやこれから音楽と同じようにパンク的な価値観、「客を笑わせるだけじゃないぞ」というアティチュードの芸人さんが増えていって、既成概念にとらわれない新しいタイプの音楽と融合する可能性もある気がしてきました。
なるほど! すごくワクワクする話ですね。
──「M-1グランプリ2021」で決勝まで残ったランジャタイは言わずもがな、マヂカルラブリーの野田クリスタルさんが師匠と仰ぐモダンタイムスもしかり。先日「スッキリ」に出演した虹の黄昏は、怒髪天の増子(直純)さんに「面白い面白くないは関係ない」と評されていました(笑)。
そうですね。でも難しいと思うのは、今名前が挙がった芸人さんたちもだいぶ世間一般に向けてチューニングしたことでテレビに出られているという点です。本当の地下芸人が、アンダーグラウンドヒーローのまま人気を獲得するのは今のシーンではちょっと想像できないですね。お笑い業界で働いていて、そういう市場というかシーンを作ってこれなかった申し訳なさみたいなものもあるんですけど。僕はすごく永野さんが好きなんですよ。永野さんはラッセンのネタで世に出たと思うんですけど。
──私も永野さんを最初に知ったのはあのネタでした。
あれも衣装を変えたりして、永野さんなりにものすごくチューニングした結果のネタなんですよね。それでもテレビに出たら“孤高のカルト芸人”みたいな扱いになっちゃうので。昔の永野さんのネタのままだったら、嫌な気持ちになっちゃう視聴者もいるだろうし。
──永野さんの昔のネタはどんな感じだったんですか?
僕が主催のライブに永野さんをお呼びするときは、「もんたよしのりさんのお葬式を想像でやってみる」という初期のネタを必ずリクエストするんです。「ダンシング・オールナイト」を流すんですけど、リハーサルのとき永野さんが音響さんに「できる限り大きい音にしてください」とオーダーして。だから本番は信じられないくらい爆音なんですよ。お葬式に来る人全員を永野さんが1人で演じて、口々に「もんたー!」とか叫んでるんですけど、客席にはまったく聞こえない(笑)。そのうち警備員とかドラム叩いてるやつとかも出てくるんですけど、ずっと爆音で。とんでもなく面白いです。
「禁断の領域」に踏み込む芸人への驚きと憧れ
──2017年には大竹さんがマネージャーをしているラブレターズが3カ月連続でおとぎ話、フレンズ、ONIGAWARAと対バンイベントを開催したことがありました。
やはり、コラボというよりは勝負になった印象がありました。初回はラブレターズが先にやって、次におとぎ話だったんです。最後に演奏した曲が「COSMOS」だったかな。すごくいいライブで。終演後に関係者の人が「いいイベントだったね!」と声をかけてくれたんですけど、号泣してるんですよ。音楽に軍配があがっているように感じました。
──バンドと芸人さんだとなかなか相乗効果が得られないと。
「やついフェス」は先日も現場にいったけど盛り上がってました! もちろん音楽に造詣が深いやつい(いちろう / エレキコミック)さんが主催してることも大きいし、音楽とお笑いでしっかり時間を分けているのも重要なんじゃないかと思います。
──大竹さんはお父様の大竹まことさんが所属するシティボーイズのライブの劇伴を担当されたことがありますよね。
2015年の「燃えるゴミ」のときですね。オープニングとエンディング、ネタの間の曲も全部作りました。エンディングのクレジット映像のBGMをアンビエントっぽい打ち込みにしたんですが、音響監督に「ここは音楽の時間だから、ちゃんとメロディがあったほうがいい」とダメ出しされたんです。すごいなと思ったんですよ。コントライブとひと口に言っても「ここはお笑いの時間」「ここは音楽の時間」という区分がはっきりとあって、その組み合わせで全体ができあがっているんだなと。
──アーティストにもお笑いが好きな人が本当に多いですよね。細野晴臣さんもお笑い好きで、1980年代にフジテレビのネタ番組「THE MANZAI」にトリオ・ザ・テクノとしてYellow Magic Orchestraが出演していましたしね(笑)。音楽家のお笑い芸人へのリスペクトって独特なものがあるように思うんです。
確かに独特のリスペクトを感じますよね。もしかすると、“お客さんをコントロールする”という領域に踏み込んでいることに対するリスペクトなのかも。
──「そこに立ち入っちゃうの!?」という、ある種の驚きと憧れのような。
そうかもしれないですよね。このあたりの話をお笑い好きなミュージシャンの方にも聞いてみたいです。スカートの澤部渡さんとか、GENTLE FOREST JAZZ BANDのジェントル久保田さんとか。
──大竹さんが提示してくれた「音楽とお笑いの緊張関係」という視点はとても重要なので、今後もいろいろな人に聞いていきたいと思います。
今日お話しするにあたっていろいろなことを思い返してたんですけど、僕は高校2年生のときにThe Offspringとかメロコアのコピーバンドをやっていたんです。そのバンドが学園祭のトリとして出ることになって。僕らの前が3年生の先輩のバンドだったんですけど、ベースアンプの位置を動かしたりして、持ち時間をかなりオーバーしていて。こっちの持ち時間も削られるから、だんだんイライラしてきたところで、先輩のバンドが「アイスマン」っていうオリジナルソングをやり始めて、それが6分くらいあったんですよ(笑)。「長いぞ!」ってみんなでキレて、2年生と3年生の抗争に発展した「アイスマン事件」というのを思い出しました。
──いい思い出ですね。
後日、大学生の頃に東京厚生年金会館にジョン・ゾーンを観に行ったら、喫煙所にそのアイスマンのベースの人がいたんです。話しかけずにそっと離れましたけど。アイスマンとオフスプリングがジョン・ゾーンでまた出会うなんて、音楽ってやっぱり懐が深いですよ(笑)。
大竹涼太(オオタケリョウタ)
芸能プロダクション・ASH&Dコーポレーションの代表取締役兼マネージャー。2007年から2014年までは人力舎で山崎弘也(アンタッチャブル)、ゆってぃなどのマネージャーを担当し、テレビ朝日「ロンドンハーツ」などバラエティ番組にも出演。2008年からテレビ東京「ゴッドタン」の「芸人マジ歌選手権」に角田晃広(東京03)とのユニットで参加し、2009年9月にはシングル「若者たちへ」でメジャーデビューを果たした。またバンド・Sensitive Brothersのギター&ボーカルとしての一面も持つ。父はシティボーイズの大竹まこと。

関連記事

佐久間大介&日村勇紀がストリートダンスの魅力学ぶ、番組オリジナル曲でパフォーマンス

GEZAN新アルバム「I KNOW HOW NOW」の収録曲発表、青葉市子らゲスト参加

「ROOTS66」会見に小泉今日子、大槻ケンヂ、斉藤和義ら66年生まれの19名ずらり!語られた“丙午”の一体感

SixTONES京本大我と松村北斗が漫才バトル、松井ケムリ&水卜麻美アナを巻き込んで

いよいよ4位から1位まで発表!今夜の「EIGHT-JAM」は“プロが選ぶ年間マイベスト10”後編
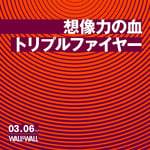
想像力の血とトリプルファイヤー、表参道WALL&WALLでツーマンライブ

ヒャダインが「カンブリア宮殿」新MCに就任「知識や気づきを曲作りにも転用させようと虎視眈々」

15年目「やついフェス」まずはKIRINJI、サニーデイ、柏木ひなた、Negiccoら30組出演決定

「ニノなのに」でM!LK佐野、塩﨑、曽野が日光名所をなるべく訪問 ACEes佐藤龍我は3日間1000円で生活



