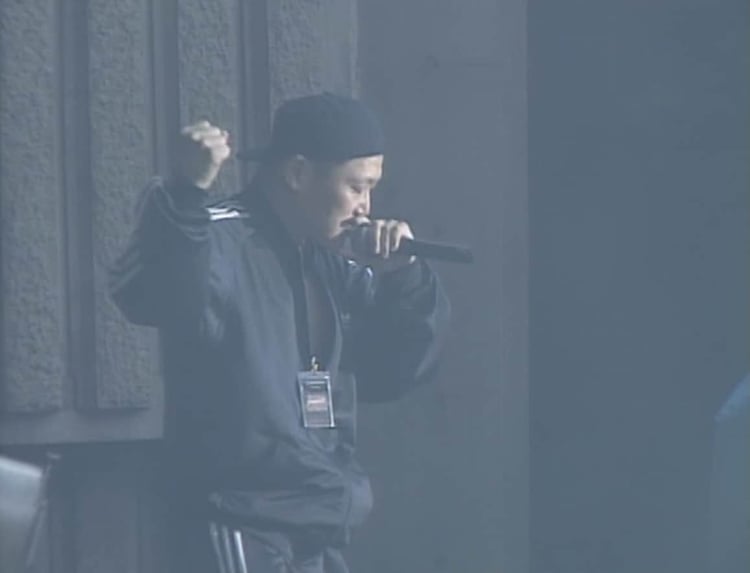伝説のヒップホップイベント「さんピンCAMP」の全貌に迫るべく、当時の関係者や出演アーティスへのインタビューなど、さまざまなコンテンツをお送りする連載企画「『さんピンCAMP』とその時代」。全3回にわたる初回は、元cutting edgeの本根誠氏、執筆家 / DJの荏開津広氏、アートディレクターの光嶋崇氏という、「さんピンCAMP」の立ち上げに深く携わった3人の鼎談をお届けしてきた。
後編にあたる本稿では、「さんピンCAMP」開催以降に“さんピン勢”という概念や“東京vs地方”という構図が生まれたワケ、ヘッズなら一度は耳にしたことがあるであろうECDの「J-RAPは死んだ、俺が殺した」という言葉に込められた思い、「さんピンCAMP」がのちのヒップホップシーンに与えた計り知れない影響について掘り下げる。
取材:高木“JET”晋一郎+猪又孝 文:高木“JET”晋一郎 撮影:沼田学 制作協力:本根誠
「さんピンCAMP」は東名阪ツアーだった
──「さんピンCAMP」は東京に加えて大阪と名古屋でも開催されたということですが、「さんピンCAMP」はツアーだったということですか?
本根誠 そうです。セールスプロモーション上の都合で、「じゃあ名古屋と大阪でもやろうか」って。
──イベントに先駆けて発売されたコンピレーションCD「さんピンCAMP ECD PRESENTS THE ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK」のプロモーションだったと。
本根 そうですね。
荏開津広 俺も行きましたよ。
──出演者は東京と違ったんですか?
本根 基本的にcutting edgeに所属していて、「アゴアシマクラは出すから、ちょっと出てくれない?」みたいな感じでもOKしてくれたアーティストでしたね。
荏開津 でも、RINOさんは来ましたよね?
本根 たぶん友情出演ですよ。ノーギャラで出てくれたはず。要するに予算を東京で使い切って、大阪、名古屋公演は出演者にあらかじめギャラを提示できなかった。結局チャージバックにして、当日の売り上げをお店と出演者で最後に割るという方式になって。ライブハウスのバンドマンと同じですよ。
荏開津&光嶋崇 ええー!
荏開津 逆に言えば、地方での集客が未知数だったということですよね。
本根 そう。でも名阪も回らないと販売促進部に叱られるから(笑)。
──名阪公演の映像を撮らなかったのはどうしてなんですか?
本根 石田さん(ECD)にその発想がなかったんじゃないですか?
光嶋 僕は日比谷でおしまいだと思ってた。
──ドキュメントとしては野音が決着だったと。
本根 ツアーでもいろいろありましたね。SHAKKAZOMBIEのOSUMIくんの声が出なくなっちゃって、YOU THE ROCK★が「お前のことをみんな待ってるんだよ!」って励ましたり。あと、DEV LARGEが楽屋の壁にタグを描き始めちゃって、そしたら俺も俺も!ってみんな真似しだしたこともあった(笑)。あれも大変でしたね。
──地元のラッパーに出てもらおうとか、そういう感じではなかったんですね。
本根 それも石田さんの発想になかったんだと思う。観に来たアーティストはいたと思うけど。
イベント開催後に生まれた“さんピン勢”という概念
──「さんピンCAMP」が話題になったことで、出たアーティストと出ないアーティストで、注目度の変化が生まれることになり、“さんピン勢”という概念や、“東京中心のシーンと、それに対抗する地方”という構図が生まれたとも思うのですが、その部分はいかがでしょうか?
荏開津 その“さんピン勢”に入らなかったのって例えば誰?
光嶋 NAKED ARTZとかかな。
──ZINGIもそうですよね。ECDと同じファイルレコードに所属していた、「CHECK YOUR MIKE」の第1回優勝者ですし。
光嶋 だからけっこういるんですよね。当然だけど。
荏開津 そうそう。「そこは入れないんだ」みたいなのは当時もあったと思う。だからMummy-Dが「さんピンCAMP」のMCで「日本のヒップホップシーンは俺たちだけで作ってるもんじゃねえ!」と言ったのは、そういう気持ちが込められてると思います。あと“さんピン勢”という流れで言えば、2000年代だったかな、同じくRHYMESTERのMC2人がラジオで「自分たちはさんピン世代だと」と自嘲気味に話してたのを覚えてます。その後それぞれ現役でやっているのに90年代の1回のイベント「さんピンCAMP」で括られるのも本人たちからしたら困惑もあると思います。あの日、野音にみんなが一緒にいたこと自体も、全員が居心地よかったかといえば、決してそうじゃなかったと想像できる。「なんで、こんなふうに一緒くたにされるんだ?」みたいな思いも感じてたとしても自然だと思います。
光嶋 それはそうですね。でも、見る側が、1つの塊として捉えるのもわかる。
──それだけ情報が少なかったのと、「さんピンCAMP」の影響が強かったということでもありますね。
荏開津 “さんピン勢”という概念が強烈な一方、「さんピン」には出なかったラッパ我リヤはその後Dragon Ashにフィーチャーされてブレイクするし、同様に石田さんが選ばなかった流れが、KICK THE CAN CREWやRIP SLYMEといった新しい日本語ラップを作っていったのも歴史的な事実です。むしろその側面は非常に大きい。本根さんが言うように“さんピン勢” に“ロック感”があったとしたら、それは既成のものへのカウンターを前面に押し出すということなのかなとも思います。
──その流れで伺うと、NAKED ARTZやラッパ我リヤはライター / クリエイターの萩谷雄一さんがコンパイルしたアルバム「悪名」に参加しました。CRAZY-AやZINGI、DS455は「ベスト・オブ・ジャパニーズ・ヒップホップ」シリーズに収録されています。TWIGYなど、アーティストによってはクロスしているのですが、「さんピンCAMP」収録勢も、そこには独特のカラーがありますね。
本根 コンピのライバルと言ったらそれぐらいですよね。特に「『悪名』よりは売れてるように見せなきゃ!」とは思ってました。予算は少なかったですけどね。
「J-RAPは死んだ」というECDの発言に込められていたもの
荏開津 cutting edgeはそんなにカツカツだったんですか?
本根 カツカツでした(笑)。TRFとか安室(奈美恵)ちゃんがいる部署は悠々自適だったけど、cutting edgeにはそういうアーティストがいなかったんで。
──2000年にcutting edgeからデビューしたMICADELICのDARTHREIDERも、「俺らは同じcutting edgeに所属してたJanne Da Arcに食わせてもらってた」と言ってました(笑)。ただ、売上の高いアーティストの収益をほかのアーティストの制作予算に充てるというのは、予算の循環として普通にあることです。
光嶋 その流れで言えば、僕はMUROくんのソロアルバム「Pan Rhythm: Flight No.11154」のジャケットデザインを手がけたんですが、海外ロケとかかなりいろんなチャレンジができた。それもトイズファクトリーがミスチルで大儲けして、予算が潤沢にあったからなんでしょうね。
荏開津 アーティスト側にも“俺たちを使うメジャー業界”みたいな意識があったんじゃないかな。それこそ「証言」でも歌われているような感じで。真偽はともかく幾人ものラッパーの人から実際にそういう話を聞いたこともあります。
本根 ECDやユウちゃんはcutting edgeにお金がないことがわかってたから、僕らに対して敵意はなかったと思うけど、外に出ると「お前、エイベックスにいいように使われてないか?」とか言われてたと思いますよ。でも僕はレコード会社の社員として悪役のイメージを持たれてもいいと思ってましたね。なんかギラついたイメージのほうが目立って、結果アーティストに注目が集まるのかな、と。
──特にエイベックスはm.c.A・T「Bomb A Head!」をリリースしていたレーベルですからね。
荏開津 そういう部分も、石田さんが決めた「さんピンCAMP」というタイトル然り、イベント冒頭での「J-RAPは死んだ、俺が殺した」という言葉も然り、いろんなことにつながってくるような気がする。
本根 そういう役割を担おうとしたんでしょうね。一番アンビバレンツを持ってたのは石田さんだったと思います。だからこそ生まれたイベントかもしれない。
──「J-RAPは死んだ、俺が殺した」という「さんピンCAMP」の1つのテーゼやアティチュードについて、スタッフ間で話はされたんでしょうか。
荏開津 いや、僕は何も話してない。特に「殺す」という言い方には驚いてそこまで強い言い方をしなければならないのか、と当時正直思ったけど、それはラップという技術ではなくヒップホップという“価値観”を提示するための試行錯誤の1つだったんだな、と今は思います。
光嶋 でも、全員「J-RAP」と言われる曲をクソダサイと思っていたはずですよ。少なくとも僕はJ-RAPと呼ばれる楽曲をまったくカッコいいと思っていなかった。だから僕らが言葉にできないような気持ちを石田さんが代表して言ってくれたと僕は思ってます。
BUDDHA BRANDは松本隆の次の世代を担う存在になると思っていた
本根 でも、BUDDHA BRANDに関してはポップ層にも通用すると思っていましたよ。会社やECDにも言ってなかったけど、ブッダは松本隆の次の世代を担う存在になると。はっぴいえんどから出発して、歌謡曲でもたくさん素晴らしい歌詞を書いて、ヒットメーカーになった松本隆のように、ブッダもそういう存在になると思ってた。
──それは興味深いですね。
本根 BUDDHA BRANDの初期の曲って、ドギツイ内容もあるけど、人を懲らしめようとしてるんじゃなくて、結局は、みんなで楽しもうよと歌っているわけじゃないですか。だからハードコアなんだけど、パーティソングの側面が強い。特にNIPPSとCQのパートは、かつて松本隆が歌詞で提案したような若者のライフスタイル──つまり“その次の世代”の感覚をリアルに描いているんじゃないかと思っていたんです。このまま活動を続けていって、「人間発電所」を超えるシングルヒットが生まれたら、松本隆の次の世代の価値観を、このグループは提示できるかもしれないと思ったんですよね。もうディレクターの妄想力。でもそれぐらいの気概で作業していたんです。でも「ブッダの休日」はあまり芳しい反応がなくて、その次にトヨタのタイアップが決まっちゃったんです。
荏開津 「天運我に有り(撃つ用意)」ですね。
──NIPPSさんが脱退され、ラッパーはDEV LARGEさんとCQさんの2人体制での制作になりました。
本根 あの曲で、DEV LARGEのガンバリズムみたいなマインドがグループの歌詞を覆うようになったし、それをリスナーも求めるようになった。そしてDEV LARGEが、さらにガンバリズムみたいな歌詞を書くようになって、パーティソングっぽさがなくなっていっちゃったんですよね。そこで僕の心の中にあった「ブッダが松本隆を超える」という夢は、ついえてしまった。でもガンバリズムでさらに広く注目されたのも事実なんですが。
光嶋 なるほど。あと、これは30年越しに聞きたかったんですけど、「さんピンCAMP」のVHSって売れたんですか?
本根 売れたんじゃないのかな?(笑)
荏開津 なんで担当ディレクターが知らないの!(笑)
本根 ふふふ。社内では叱られもしなかったけど、「すげーすげー」と言われたことはないですね。
光嶋 でも、今の日本語ラップシーンの盛り上がりに直接つながってるのは「さんピンCAMP」だと思うんですよね。
荏開津 それは絶対そうでしょ。
光嶋 晋平太さんは「『さんピンCAMP』が決定的だった」みたいなことをYouTubeでも言ってくれていて。その晋平太さんを見て、フリースタイルを始めた人は確実にいるわけでしょ?
荏開津 そうそう。若者が何か言いたいことがあったら、韻を踏んで言えばそれがメッセージになり、音楽になるというのは、「さんピン」の時期に生まれた作品から広まった価値観だと思う。そして、それがより広まって、バズって、お金を生むようになっているのが今ですよ。
「さんピンCAMP」の頃には、リアルな現場でしか人とのつながりが生まれなかった
──すごく大づかみな質問になってしまうんですが、「さんピンCAMP」が開催された1996年は、どんな時期だったと思いますか?
本根 多忙だったせいか、覚えてないな……(笑)。でも1996年に比べて、2025年はものの見方が確定的になってると思いますね。やってみないとわからないということが今は少なくなってる気がする。
光嶋 数字が全部出ちゃいますからね。
本根 だからか、レコード会社にも、失敗はしないけれど大成功もしないディレクターが多い。僕がいた95、96年当時のcutting edgeのヒップホップアーティストで、しっかり黒字が出たのはBUDDHA BRANDぐらい。ブッダはとにかくカッコいいグループだったけど、それでも売れるかどうかの予測は不可能でしたよ。
光嶋 だからトライ&エラーが許された時代なんじゃないですかね。1996年って。
荏開津 僕自身はアシッドジャズをDJの中心にしていて、小林径さんや鄭秀和さん、スカパラの青木達之さん、ジェームズ・ ヴァイナーと「routine」というイベントをやってました。プラス、毎日どこかのクラブに遊びに行ってた。
本根 レーベルの人間も仕事が終わると「音、聴いてから帰るわ」ってよく言ってましたね。音楽を聴く場所として、クラブをすごく大事にしてた。
荏開津 今みたいにネットもないし、音楽好きな人が集まれる場所が限られてたから、自然とみんなクラブに集まってた。それは音楽の評価もホームリスニングだけじゃなかったということだと思います。
光嶋 今はインターネットでいろんな人とつながれるじゃないですか。でも「さんピンCAMP」の頃には、リアルな現場でしか人とのつながりが生まれなかった。
荏開津 そうだよね。あと、当時はストリートカルチャーと経済がリンクし始めた時期だった。自分が縁のあったロンドンのシーンもそれ以前のイリーガルなレイヴみたいなものがいろいろな理由で終わっていって、象徴的だと思うけど現代美術家のダミアン・ハーストが作ったカフェができたりした。ストリートのアンダーグラウンドカルチャーみたいなものが一旦終わる。でも、アンダーグラウンドを礼賛してるのではなく、例えば1980年代終わりのレイヴに持続性があったのかこれを読んでる人に残ってる映像とかを観てもらいたいぐらい。日本のヒップホップもそういう意味で、前衛として役割を果たす人たちもいれば、カルチャーとしてどう経済とリンクして持続していくのかを考えた人たちもいたということでしょ。あと東京は東京でラップを包含していたより大きなクラブシーンにいた人たちがそれだけに飽き足らず、スタイリストになったりとか、洋服を作ったりとか、そういう流れが90年代に始まった。タカちゃんの周りにいたNIGOさんとジョニオさん(高橋盾)が伝説的な店、NOWHEREを出したのはその時代です。
光嶋 そうですね。シンちゃん(滝沢伸介)もNEIGHBORHOODを立ち上げたり、周りの友達がみんな有名になっていった。僕もBMWに乗ってたし、ラジオもテレビのレギュラーもある、「さんピン」も撮ってるという感じで、今までで一番忙しかった。でも、ヒップホップ自体は流行ってなかったと思います。
荏開津 そうだね。
光嶋 流行ってる感じじゃないし、言っとくと「さんピン」のギャラが一番安かった(笑)。
(一同爆笑)
荏開津 僕が当時考えてたのは、「ラップがなんでメジャーにならないんだろう?」ということ。それはずーっと思ってた。ようやく最近メジャーになってきたけど、めちゃくちゃ時間がかかってびっくりしてる。
光嶋 今はラップという表現が普通になってますもんね。うちの子供もやりますもん。水曜日のカンパネラさんを真似して。
荏開津 もっと早くそういう状況になると思ってた。
「さんピンCAMP」が生み出したものとは?
──最後に、「さんピンCAMP」が生み出したものは、制作者としてはなんだったと思いますか?
光嶋 「LEGEND OF JAPANESE HIPHOP」という「さんピンCAMP」のサブタイトルは誰が考えたんですかね?
本根 僕なのかECDなのか……でも、そういう意識はあったんでしょうね。「伝説化するぞ」みたいな。
光嶋 僕が映像を撮ってる当時は、まさかここまで、のちのヒップホップシーンに影響があるとは思ってませんでした。でも今こうやって取材を受けているということは、「さんピン」というイベントが、開催から約30年という時を重ねることで、より伝説化しているということですよね。そして、その後のシーンに大きな影響を与えた人たちをフックアップしたイベントだったからこそ伝説になってる。MUROくんが、のちにNITRO MICROPHONE UNDERGROUNDにつながるメンツを、ユウちゃんが雷を、Kダブがキングギドラを、ECDが四街道ネイチャーを……みんなでフックアップし合ったことで、現場にいた人はもちろん、映像を観た地方の子供たちにも、ヒップホップカルチャーを届けたという。
荏開津 僕は当時から「さンピンCAMP」は伝説のイベントになるだろうなと思っていました。ラップをすることが当たり前になってほしかったし、最初にライミングみたいなものを自分たちで工夫して作った子供たちが伝説になっていくのは、当然それに値する行為だと思ってた。
光嶋 うん、当の出演者はそう思ってなかったかもしれないですけど、本当にそう思います。
荏開津 タカちゃんは伝説(スチャダラパーのBose)が隣にいたからね。
光嶋 いやいや、生まれたときから一緒にいるからそんなこと全然思ったことないです(笑)。
荏開津 僕からすればタカちゃんだって伝説だよ。
光嶋 えー! いやいやいや(笑)。
荏開津 みんな伝説です、本当に。自分たちだけじゃないけど、みんなでヒップホップを作ったんだもん。
本根 僕も荏開津さんの意見に近いかな。The Velvet Undergroundって全然売れたバンドじゃないけど、ヴェルヴェッツのレコードを買った連中がみんなバンドを始めてるみたいなさ。イベント自体がそんな存在になったんじゃないかな。僕はフツーのポップ少年だったからシングルヒットも出したかったし、いい契約でラッパーのみんなが車を買える環境を作りたかった。それを当時は実現できなかったけど、結果的に「さんピンCAMP」を通して、いっぱいクリエイターが生まれたならそれはすごくうれしいことで。
光嶋 そうですよね。
荏開津 この対談を読んでも僕が「さンピンCAMP」で実際に何をしていたのかわからない人が多いと思う。最初にECDに方向性について相談を受けたのをサジェスチョンしたのと、あとは自分のDJの合間にただ現場にいただけだと言えるから恥ずかしいです。そんな自分については弁解もない。ただし「さんピンCAMP」の役割は歪なところがあったとしても日本のポップ音楽の歴史においてすごく大きかったと思いますし、自動翻訳機もないしYouTubeの解説家たちさえいなかった当時を振り返ると、歪な形でしかプロジェクトを実現できなかったのも仕方ないとも思います。「さんピンCAMP」は「ヒップホップとは何か?」をなんとか形にして提示したことだと自分は思っています。
本根誠
1961年大田区生まれ。WAVE、ヴァージンメガストアなどCDショップ勤務を経て、1994年、エイベックスに入社。cutting edgeにてディレクターとしてECD、東京スカパラダイスオーケストラ、BUDDHA BRAND、SHAKKAZOMBIE、キミドリ、Fantastic Plastic Machineなど、さまざまなアーティストを手がける。「さんピンCAMP」では、主催者であるECDを担当ディレクターとしてサポートした。独立~東洋化成を経て現在、再びエイベックス勤務。
本根誠 Sell Our Music _ good friends, hard times Vol.9 - FNMNL
荏開津広
東京生まれ。執筆家 / DJ / 立教大学兼任講師。東京の黎明期のクラブ、P.PICASSO、MIX、YELLOWなどでDJを、以後主にストリートカルチャーの領域で国内外にて活動。2010年以後はキュレーションワークも手がける。「さんピンCAMP」では、スーパーバイザーとしてコンセプトや構成に携わった。
荏開津広_Egaitsu Hiroshi(@egaonehandclapp) | X
荏開津広_Egaitsu_Hiroshi(@egaitsu_hiroshi) | Instagram
光嶋崇
岡山県出身。アートディレクター / 大学講師。桑沢デザイン研究所卒業後、スペースシャワーTV、レコードショップCISCO勤務を経て、ドキュメンタリー映画「さんピンCAMP」を監督。のちにデザイン事務所設立。スチャダラパー、MURO、クボタタケシ、かせきさいだぁ、BMSG POSSEなどのデザインを手がける。
designjapon.com
光嶋 崇(@takashikoshima) | X
光嶋 崇(@takashikoshima) | Instagram
※文中のアーティスト表記は、原則的に「さんピンCAMP」開催当時に沿っています。

関連記事

Base Ball Bearライブに岡村靖幸とRHYMESTER出演決定

MUROが“レアグルーヴ”観点で掘り起こした、アルファ音源コンピ盤「DIGGIN' ALFA」発売

DJイベント「申し訳ないと」が年内で活動終了、「30周年パーティー」に宇多丸やtofubeatsら

ラッパーXBS、保育園の園長になる

Perfumeと音楽ナタリーの18年――ライブレポートで振り返る、熱狂の日々の全記録

大神3人が振り返る「さんピンCAMP」ライブ当日の記憶

SHAKKAZOMBIE・TSUTCHIEのソロ1stアルバムがサブスク解禁 スチャ+ロボ宙、曽我部恵一、ECDら参加

ブッダとシャカの邂逅から生まれた伝説のユニット、大神とはなんだったのか

Kダブシャイン「自主規制」15周年記念盤リリース、KGDR「アポカリプス ナウ」など追加